びおの珠玉記事
第174回
夏の野菜と果物
※リニューアルする前の住まいマガジンびおから珠玉記事を再掲載しました。
(2009年06月26日の過去記事より再掲載)
えだまめ

枝から切り離すと一気に味が落ちるので、枝付きで買ってきて家でさやを取るのが、おいしく食べるポイント。うまみが流出してしまうので、ゆですぎは禁物。新鮮さが命なので、買ったその日に食べるのがよい。
選び方
枝から切り離すと一気に味が落ちるため、なるべく枝付きのものを購入するとよい。
枝にサヤがたくさん付いていて、緑色が濃く鮮やかなもの、豆がふっくらとしていて、うぶ毛が濃いものを選ぶ。
オクラ

選び方
緑色が濃くうぶ毛が多いもの、皮に張りがあり、角がはっきりしていて、適度にやわらかいものを選ぶ。ヘタの切り口がみずみずしく、黒ずんでいないものがよい。
かぼちゃ

冬至にかぼちゃを食べる風習は、かぼちゃは保存性が高いので、冬まで保存し、緑黄色野菜の少ない冬にビタミンを補給しようとした昔の人の知恵。豊富に含まれるカロテンが風邪予防に役立つ。
選び方
ずっしり重く、皮がかたくて、緑色が濃く色むらがないものを選ぶ。ヘタが乾いていて周りがくぼんでいるものは完熟後に収穫された証拠。
カット売りのものは、ふっくらとした種が詰まっていて、果肉の色が濃いものを選ぶ。果肉は赤みが濃い方が甘い。
カットされたものは、早めに使う。
きゅうり
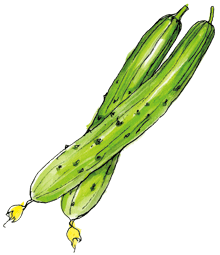
1年中手に入るが本来の旬は夏で、旬のものは冬場のものよりもカロチンやビタミンCなどを多く含んでいる。みずみずしさとシャキシャキとした歯ごたえが魅力。
果菜類の中で消費量はトップクラス。「白いぼきゅうり」が流通の約9割を占める。「板ずり」をすると色が鮮やかになり、青臭さやイボが取れ、味もしみやすくなる。きゅうりは体にこもった熱をとるので、熱中症によい。また利尿効果があり、むくみの解消に効果がある。
選び方
太さが一定で、イボがとがっていて触ると痛いくらいのものが新鮮。緑色が濃くてツヤがあり、表面に張りがあるもの、ヘタの切り口がみずみずしいものを選ぶ。
くうしんさい(空芯菜)(ようさい、えんさい)
葉はやわらかく、茎はシャキシャキとした歯ごたえがあり、アクもクセもなくて食べやすい。すぐに火が通るので、手早く調理し、独特の歯ごたえがなくならないようにする。加熱しても鮮やかな緑色はほとんど失われない。
ビタミン類やミネラルが豊富。特にカロテンが非常に多い。腸を整える他、貧血予防効果が知られている。
選び方
葉がみずみずしく鮮やかな緑色で、張りがあり、茎がまっすぐに伸びたものが新鮮。
ゴーヤ(にがうり)
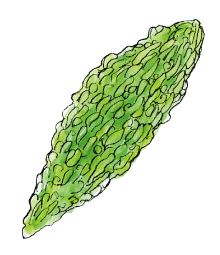
ビタミンCの含有量がとびぬけて多い。(トマトの約5倍)しかも加熱しても失われにくいという特徴があるので、栄養面を気にせずさまざまな料理を楽しめる。
苦みの成分モモルデシンには消化液の分泌を促して食欲を増進させたり、血糖値を下げたり、肝臓の働きを活発にするなどの働きがある。
選び方
緑色が鮮やかで、太さが均一なもの、イボがしっかりしていて、張りとツヤがあるものを選ぶ。
さやいんげん
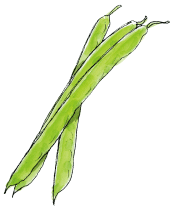
ビタミン・タンパク質・ミネラルなどを豊富に含む上に、食物繊維も多く、栄養価の高い緑黄色野菜。
種まきから収穫までの期間が約60日と短く、年に3回もとれるため、別名「三度豆」とも呼ばれる。
選び方
サヤの緑色が濃く、先がピンとしていてみずみずしいものを選ぶ。黒い斑点やシミの出ているものは古いので避ける。
しょうが

日本では、それ自体を食べるのが目的の新しょうがや葉しょうがも夏に出回る。香辛料としてよく使う根しょうが(ひねしょうが)は、新しょうがを貯蔵したもので、通年出回る。
殺菌や解毒、解熱、発汗、抗酸化作用があり、炎症も抑える。辛みや香りの成分は胃を刺激して消化液を分泌させ、腸の調子も整える。食欲増進の効果があり、夏バテ防止に役立つ。また、血行をよくして体を温めるので、風邪の時にしょうが湯などにして飲むのもよい。刺身などに欠かせない薬味。魚の生臭さ、肉の臭みを消す効果もある。たんぱく質を分解する酵素の働きによって肉をやわらかくする。
選び方
根しょうが:あめ色でツヤと張りがあり、表面がなめらかなもの、実がぎっちりとしまっているものを選ぶ。葉しょうが:みずみずしく、葉や茎にツヤがあるもの、緑・赤・白の色がはっきりしているものを選ぶ。
しそ
独特のさわやかな香りがあり、日本では最も知られている香味野菜のひとつ。
香りの成分ペリルアルデヒドに強い殺菌作用と食欲増進作用がある。ビタミンやミネラルが豊富で、特にカロテンとカルシウムが多く含まれている。
選び方
緑色が鮮やかで全体に張りがあり、葉先までピンとしていて、切り口が変色していないものを選ぶ。
葉の裏に黒い斑点があるものは避ける。
香りが強いものほど薬味効果が期待できる。
じゅんさい
池沼に小舟を浮かべ、水中の若芽を摘むじゅんさい採りは初夏の風物詩。
特有のつるんとした舌触り・のど越しを楽しむ。涼を感じられ、食欲をそそる。
選び方
小さな葉を包んでいる粘液質が透明で、ぷるんとして張りがあり、量も十分にあるものが上質。
芽の出始めで小さいものほど味がよいとされ、珍重される。
つるむらさき
葉、茎、花軸とも食べられるが、主として葉や、つる先から15cmくらいまでの茎を食用にする。アクは少ないが、独特の土臭い匂いがあり、加熱するとぬめりが出る。
栄養価が非常に高く、近年健康野菜として注目されている。カロテンとカルシウムが特に豊富。
選び方
葉が肉厚でツヤがあり緑色が濃いもの、茎が太くてツヤのあるものを選ぶ。茎の切り口が乾いていたり変色したものは避ける。
とうがらし
とうがらしの成分として注目されている辛みの成分、カプサイシンは、新陳代謝を活発にし、血行を促進して体を温めたり、体脂肪を分解する作用がある。
選び方
表面にツヤと張りがあるものを選ぶ。切り口やヘタが黒ずんでいたり、やわらかくなっているものは古く、香りも落ちる。
ピーマン
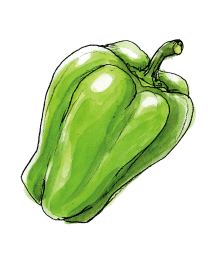
炒め物、煮物、揚げ物など、どんな調理法でもおいしく食べることができる。
ビタミン類やミネラルが多く、におい成分のピラジンや辛味成分のカプサイシンなども含む。これらには様々な作用があり、とても体によい野菜の1つ。特にビタミンCは豊富で、大きめのピーマン1つでレモン1個分以上のビタミンCを摂れる。しかも肉厚なので加熱してもビタミンCが失われにくい。
選び方
色つやがよく張りがあって果肉が厚いもの、ヘタの切り口が新鮮なもの、全体的にふっくらとしているものを選ぶ。
ししとう

ビタミンCやカロテンが豊富なので、夏場の疲労回復に効果的。
京野菜の「伏見甘」や大ぶりで肉厚の「万願寺」もししとうの仲間。
選び方
緑色が鮮やかで色つやがよく、張りがあり、においがはっきりしているものが新鮮。ヘタが黒ずんでいるものは避ける。
とうがん
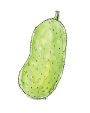
旬は夏だが、涼しいところに置くと保存がきき、野菜の乏しい冬でも食べられるので「冬瓜」という字を用いる。
選び方
緑色が濃く、表面にツヤがあり、ずっしりと重みがあるものを選ぶ。
とうもろこし
鮮度が命。収穫するとすぐに糖分が減りはじめ、半日で甘味が半減すると言われるほど。栄養価も落ちていくので、できれば皮つきで、採れたての新鮮なものを選び、すぐに調理したい。皮とひげは加熱する直前に取る。カロリーが高く、タンパク質やビタミン、ミネラルも豊富。
選び方
できるだけ皮つきで、葉の緑が濃いものを選ぶ。ひげの量が多く色が濃いものは、実がつまっていて、よく熟している。実は先の方までびっしりついていて、隙間がないもの、粒ぞろいで大きいものが良品。切り口や皮が黄色くなっているものは古い。
トマト
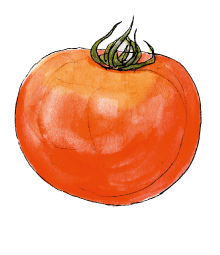
ハウス栽培なども盛んに行われているため一年中出回っているが、やはり夏が旬の露地栽培のものは格別。多様な栄養素を含むため「トマトが赤くなると医者が青くなる」と言われる。
選び方
ヘタが緑色でピンと張っていて、切り口も新鮮なものがよい。赤色が濃く、全体が丸くて張りがあり、重量感があってみずみずしいものを選ぶ。
「桃太郎」は、へたの周りに少し緑色が残っているものが、甘味と酸味のバランスがよい。
みょうが
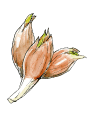
独特の香り、軽い苦み、シャキシャキとした歯ざわりが特徴。そうめん、冷奴、刺身などに夏の薬味として欠かせない。甘酢漬けにしたり、汁の実や天ぷらでもおいしく食べられる。
香り成分のアルファピネンには、食欲増進、消化促進、発汗作用、血行促進作用がある。
選び方
小ぶりで丸みがあるもの、ツヤがあり色が鮮やかなもの、しっかり身がつまっているものを選ぶ。
らっきょう

他の時期には手に入らない季節感のある野菜。独特のにおいと辛み、ぱりっとした歯ごたえがある。甘酢漬け・塩漬け・しょうゆ漬けなどにして食べる。
らっきょうの辛味を抑えて育成し、葉付きで早めに収穫したものが「エシャロット」として流通している。生でそのまま味噌などをつけて食べたり、薬味や料理に使う。
におい成分のアリル化合物は、食欲を増進し、血液をきれいにし、ビタミンB1の吸収をよくして疲労回復を助ける。食物繊維も多く含む。
選び方
丸みがあり、粒が大きめでそろっているものが良い。
なす
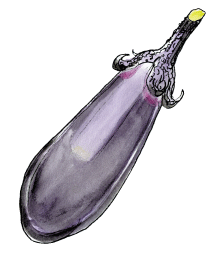
味にクセがなく、焼く・炒める・揚げる・煮る・漬けるなど調理法が幅広いのも魅力の1つ。油との相性がよい。
栄養価はあまり高くない。皮にはポリフェノールのアントシアニンやナスニンが豊富で、抗酸化作用があり、ガンや老化を防止する効果がある。
選び方
濃い黒紫色で、表面にしわや傷がなくツヤがあり、ヘタのとげが鋭く、切り口がみずみずしいものを選ぶ。
すいか
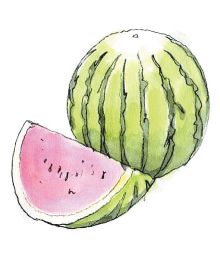
甘い果汁は即効性のあるエネルギー源になるため、夏場の水分補給・エネルギー補給に最適。抜群の利尿効果があり、体内の老廃物の排出を促してくれる。
選び方
緑と黒の縞模様がはっきりしていて、持ったときにずっしりと重いもの、ヘタの切り口がみずみずしく、ヘタの周囲が少し盛り上がっているものを選ぶ。
軽くたたいてコンコンと高い音がするものが食べごろで、ボコボコと鈍く低い音がするものは熟しすぎ。
カットされたもの:黒い種が多く、果肉の赤色のきれいなものを選ぶ。種の周りに隙間があったりくずれているものは熟しすぎなので避ける。
うめ
さわやかな香りと酸味がある。生食はしない。梅干し・梅酒・梅漬け・梅酢・梅肉など、さまざまな形に加工されて出回っている。疲労回復、食欲増進などの作用がある。
梅酒に使う場合:青色が鮮やかで粒がそろっているもの、果皮に張りがあり、みずみずしいものを選ぶ。
梅干しに使う場合:黄色く熟したものを選ぶ。
さくらんぼ
アジア西部のトルコ周辺が原産とされる。日本へは明治初期に欧米から伝わった。
初夏の到来を告げる果物。愛らしい姿で「赤い宝石」とも呼ばれる。プチンとはじけるような食感や甘酸っぱい味が魅力。
日本に多い白肉種と、アメリカやイタリアなどに多い赤肉種(いわゆるアメリカンチェリー)に大きく分けられる。
ハウス栽培された早出しのものは酸味が強く、6月中旬から下旬にかけて出回る露地栽培のものは甘味が強いとされる。生食の他、缶詰・ジュース・ジャム・砂糖漬けなど、加工品も多く出回る。
選び方
実がふくよかでしっかりしたもの、赤色が鮮やかで、皮に張りとツヤがあり、傷やへこみがないものを選ぶ。軸はしっかりと張っていて、緑色のみずみずしいものがよい。
びわ
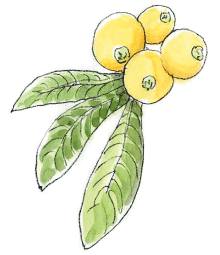
中国原産だが、一説では日本にも野生種が自生していたとされる。古くから栽培されており、平安時代の書物にもその名が記されている。
ハウス栽培のものより、初夏の露地栽培のものの方が果汁が多くて味がよい。
日持ちはしないので、買ったらすぐに食べるのがよい。
選び方
皮の橙色が鮮やかなものを選ぶ。表面のうぶ毛が取れていないものが新鮮。香りが高いものはよく熟している。
すもも
すももには多くの種類があるが、日本すもも・西洋すもも・アメリカすももの3つに大別される。
日本すももは中国原産で、奈良時代に日本に伝わったとされるが、主に観賞用・薬用で、全国に普及したのは明治時代になってから。日本からアメリカに渡り、そこで高く評価され、改良されて日本へ逆輸入された。
英語ではプラムと呼ぶ。西洋すももの果実を乾燥させて種子を抜いたものがプルーン(ドライプラム)で、栄養価が非常に高い。
選び方
丸くて、張りとほどよい弾力があり、重さのあるものを選ぶ。果皮に白い粉(ブルーム)が付いているものは新鮮。香りがよいものは熟した証拠。
ブルーベリー
紫色の色素アントシアニンは、視力低下を防ぎ疲れ目を回復させる。目によく効く果物として人気急上昇中で、国内の生産も増加傾向にある。
買ってきたら2~3日で食べきるように心がけよう。
選び方
粒に張りがあり、粒の大きさが揃ったもの、大粒なものを選ぶ(小粒は酸味が強い可能性がある)。色が濃いものほど熟している。白い粉(ブルーム)がふいているものは新鮮で食べごろ。
もも
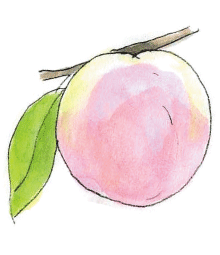
中国原産で、日本には縄文時代に渡来したと言われ、栽培の歴史は古い。国内で様々な品種改良が行われ、現在日本で栽培されているのは、ほとんどが日本オリジナルの品種。
甘さのわりには低カロリーで、豊富なペクチンは動脈硬化や高血圧予防、糖の吸収を抑えるなど生活習慣病に大きな効果がある。
選び方
傷がついておらず、きれいな球形のもの、甘いよい香りが漂っているもの、適度に弾力があり、みずみずしいものを選ぶ。うぶ毛がしっかりついているものが新鮮。
マンゴー
宮崎や沖縄、鹿児島などの国産マンゴーの旬は6月から8月にかけて。
完熟したものは痛みが早いのですぐ食べる。未熟のものは常温で追熟する。皮にしわが寄り始め、弾力が出てきたら食べごろ。
「ウルシ科」の果物のため、人によっては果汁に触れるとかゆくなったり、かぶれたりする場合もあるので、注意が必要。
選び方
色鮮やかで、なめらかでツヤがあり、ふっくらとしているものを選ぶ。
メロン
北アフリカ原産。数多くの品種がある。日本で栽培されているメロンは、温室メロン(マスクメロンなど)・ハウスメロン(アンデスメロン、夕張メロンなど)・露地メロン(プリンスメロンなど)・まくわうりに大別される。
消化がよく、豊富な糖質が即効性のエネルギーになる。疲労回復や美肌効果も期待できる。
香りが強まり、おしりの部分がやわらかくなったら食べ頃。未熟なものは、熟すまで常温で保存する。冷やしすぎると味が落ちるため、食べる直前に数時間冷蔵するとよい。
選び方
きれいな丸い形をしていて、張りがあるもの、色付きが均一なもの、花落ち部(おしりの部分)が小さいものを選ぶ。持った時にずっしりと重みのあるものが、肉厚で果汁も多い。
網目が力強く盛り上がり、均一で細かいものが美味しい。
「旬の食材 春・夏の野菜」 講談社 編 講談社、2004年
「野菜と果物を『安心』して食べる知恵」 徳江千代子 監修 二見書房、2008年
「日本のおいしい食材事典」 江上佳奈美 監修 ナツメ社、2009年
「やさい歳時記」 藤田智 監修、大田淳子 料理 成美堂出版、2007年
「旬の食材 四季の果物」 講談社 編 講談社、2004年
「野菜&果物図鑑」 ファイブ・ア・デイ協会、若宮寿子 監修 新星出版社、2006年
