びおの珠玉記事
第97回
「びお」の系譜。5人の逸話から―
※リニューアルする前の住まいマガジンびおから珠玉記事を再掲載しました。
(2012年12月26日の過去記事より再掲載)

ノロウイルスが流行している、と報じられています。手洗い励行、食品の加熱が言われ、また消毒には、アルコールでは効果が薄く、塩素系漂白剤を用いるべし、と。もちろん感染防止の策はとって然るべしですが、そこには発生したことへの対処、という視点が強いように思えます。
報道では、ウイルスの変異が流行の兆しだと伝えています。
記事では、
変異によってウイルス粒子表面の形が変わることで、過去に感染したウイルスを攻撃するヒトの免疫システムから逃れるとともに、増殖する場所の消化管に結合しやすくなるとみられる。
と伝えています。
こうした背景には、人の免疫力の衰えと、ウイルスの変異の速さ、食生活の変化など、さまざまな要因が潜んでいます。直面する事象への対処もさることながら、そうした根本をきちんと捉えていくことが肝要です。
「びお」ってどういう意味ですか?と聞かれることがあります。
当WEBサイト「びお」の命名由来は、ドイツ語で生命をあらわす「bio」から(英語でも生命は「bio」ですが、読み方が違います)。
暮らしというのは生命活動そのものです。あらためて「びお」の根底にある記事を掲載します。
空気と、水と、場所と。古代ギリシャ時代の医者「ヒポクラテス」
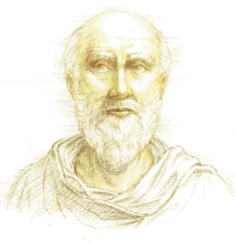
ヒポクラテス
Hippocrates
紀元前460 — 紀元前377年
(古代ギリシャの医者)
ヒポクラテス 著 小川政恭 訳
岩波文庫 発行
ヒポクラテスといえば「ヒポクラテスの誓い」が有名です。この宣誓書に接すると、医師なら誰でも背筋がピンとなるものを感じるといいます。この誓いには「医の実践を許された私は、全生涯を人道に捧げる」とか、「良心と威厳をもって医を実践する」とか、「患者の健康と生命を第一とする」といった内容が記されており、医師の使命と倫理観が今に伝えられています。
動物たちが、自分たちにいちばん適した場所に巣を設け、そのことで種の保存をはかるように、ヒトもまた場所と、建築材料を適切に選び、住まう技術を進化、発展させてきました。
縄文人は、いい風は通っているけれど強風を避ける場所や、いい水は得られるけれど水害が生じない場所を巧みに選んで住まいをつくった、といいます。
けれども、弥生時代に入ると、この国には稲作が入ってきて、容易に水を得られる場所へと住居を移動することになりました。
つまり、生産活動にとってつごうのいい場所に住まいを構えるようになったのです。
地域や国によって異なりますが、大きく歴史をみると、どこでもそんなふうに変化しました。それからというもの、人類は驚くべき進化を遂げました。
今の地球温暖化や環境ホルモンの問題は、すべて人間活動の結果生じたものだといわれていますが、自然界の物質循環のなかで生きていた縄文人のしあわせな状態から、ついにヒトは、ここまで来てしまったのか、との思いを持たざるを得ません。
人間の健康にとって「空気と水と場所」が大事なことを最初に文字に記したのは、医学の父・ヒポクラテスでした。ヒポクラテスに『古い医術について』(訳:小川政恭/岩波文庫)という本がありますが、その中に「空気・水・場所について」という論文が収められています。
この論文でヒポクラテスがいう空気とは、風(暖および寒の風)をいい、水は飲用水を意味し、場所は、地形や地質を意味します。この三つが健康にとって大きな役割を持っており、医師はその土地に赴任したらそれらを先ず調べるべきだと、ヒポクラテスは口を酸っぱくして言っています。
当時の医療は呪術的なものが支配していました。ヒポクラテスは、環境と病気の関係を観察し、自然現象の一つとして病気をみようとしました。また、病気に罹っても、人間のからだは、もともと健康に戻そうという力が備わっているといい、今でいう免疫学に近い考えを持っていたことが知られています
ドイツ人医師、ペッテンコーファーに始まる、
バウビオロギーという考え方。

マックス・ヨセフ・フォン・ペッテンコーファー
Max Josef von Pettenkofer
1818 — 1901年
(ドイツ〈バイエルン王国〉の衛生学者)
農民の子として生まれ,当初は俳優を志す。後に薬剤師となり,さらに医学を学ぶ。「近代衛生学の父」「環境医学の父」「実験衛生学の父」と呼ばれる。
それで予防医学のことを調べていたら、ペッテンコーファーという人が浮上しました。森鴎外のドイツ留学時代の恩師であり、鴎外のお孫さんは、この人のファーストネームであるマックスから真章とつけられています。
しかし、このペッテンコーファーという人、調べれば調べるほど奇妙な人であることが分かりました。実に多芸多才な人で、医学以外に金と銀とプラチナを分ける方法を見つけたり、廃材から可燃性ガスを生産する方法を開発したりと、さまざまな業績をあげています。
医学の分野では、炭疽菌、結核菌、コレラ菌の発見者として知られるロベルト・コッホ(1843—1910年)との病因論争が有名です。
ペッテンコーファーはコレラ菌の発生理論を証明するため、病原菌を自ら飲んだというエピソードを残しています。彼は残念なことにコッホの前に敗れます。コッホがノーベル賞の栄誉に輝いたのに対し、ペッテンコーファーの晩年は寂しいものとなりました。
日本では、北里柴三郎(1853—1931年)がコッホの弟子だったこともあって、ペッテンコーファーの方はあまり知られていません(日本は、感染症重視の北里という印象が強いため下水道の整備が遅れたという俗説もありますが……)。けれどもドイツでは、下水道の普及と衛生行政の発展に多大な功績をおさめた人物として、その名前は今も多くの人に知られています。
彼は、人間の代謝と栄養に関する一連の重要な実験を行っています。何しろ頭のよく回る人で、いろいろな発見・発明をしています。人体用呼吸計を開発して、炭酸ガス濃度を汚染の指標とする科学的な方法を編み出したのもその一つで、こうして彼は室内空気質と建築素材、換気の重視など、今の予防医学の考えに通じる事跡を数多く残し、ドイツのバウビオロギー建築の基礎を築いたのです。
50年前にレイチェル・カーソンさんが『沈黙の春』で書いたこと

レイチェル・カーソン
Rachel Louise Carson
1907— 1964年
(アメリカ内務省魚類野生生物局の専門官。海洋生物学者)
アメリカ合衆国のペンシルベニア生まれ。DDTなどの蓄積が招く環境悪化、食物連鎖による人間への影響など化学物質の危険性を、1962年に著書『沈黙の春』にて告発。本書を基にケネディ大統領は大統領諮問機関に調査を命じ、その後、DDTの使用は全面的に禁止された。
春がきても、鳥も鳴かずミツバチの羽音も聞こえない沈黙した春を迎えるようになるかもしれない、という寓話で始まる『沈黙の春』は、化学物質による環境汚染への、最初の警告の書でした。
この本の著者であるレイチェル・カーソンさんは、米国の内務省に務める職員でした。仕事で野生生物などを調べているうちに、DDTやBHCなどの有機塩素系殺虫剤や農薬が、野生生物や自然生態系に影響し、人間の体内に蓄積され、次世代に深刻な影響を与えることに気づきました。自分の見出したことを本に書くために、彼女は内務省から去りました。
本が出版されて驚いたのは、その原因をつくった化学業界や農薬協会の人たちでした。
1962年6月に雑誌『ニューヨーカー』に、この本の抜粋が掲載されると、たちまち賛否の議論が巻き起こり、9月に単行本が出るとその日のうちに1万部が売れました。
こういう場合のアメリカは、今もそうですが、熱狂的にマスコミが取り上げます。
化学業界や農薬協会の人たちは、多額の費用を投入して、大がかりなネガティブ・キャンペーンに乗り出しましたが、それがかえってこの本の知名度を高めることになり、ついに全米ベストセラー・ランクのトップに押し上げられることになりました。
けれども、この本の人気はマスコミによってつくられたブームのせいだけではありませんでした。それには、DDTなどの殺虫剤が空中散布されている乱暴な使用実態を、彼女は臆することなく告発したその勇気と、動かすことのできない事実の重みと、類書にはない美しく分かりやすい文章の力をあげることができます。
彼女は、「生命の連鎖が毒の連鎖にかわる」ことを書き、「食物連鎖」と「生物濃縮」を経て環境汚染が進むことを次のように綴りました。
「静かに水をたたえる池に石を投げこんだときのように輪を描いてひろがってゆく毒の波——石を投げこんだ者はだれか。死の連鎖をひき起こした者はだれなのか」
アメリカでの論争は、ケネディ大統領の科学諮問委員会の報告書が出るに及んで評価は一変し、DDTが全面禁止されるなど化学物質規制が講じられ、環境保護局(EPA)の発足へとつながりました。
『沈黙の春』が発表されて、50年になります。発表時、彼女は「ヒステリックな海洋生物学者の売名行為」と非難されました。しかし、時間の経過は、彼女が指摘したように進行し、人間活動が自然を蝕んでいる実態が世界中でみられるようになりました。
彼女の母親マリア・マクリーン・カーソンさんは、長老派教会の牧師の娘でした。その影響によるものか、彼女は生涯を通じて、お金を稼ぐために何かをするという人ではありませんでした。海を愛した彼女の遺灰は、メイン州沖に撒かれました。
30歳だったドネラ・H・メドウズさんが予測した『宇宙船地球号』の近未来。

ドネラ・H・メドウズ
Donella H. Meadows
1941—2002年
(アメリカの生物物理学者・環境学者)
カールトン大学で化学、ハーバード大学で生物物理学を修める。1972年、「成長の限界プロジェクト」に加わる。ダートマス大学環境研究プログラム助教授として、コンピュータモデルを使って社会、環境、エネルギー、農業などのシステムを研究した。
『沈黙の春』が発行された年から10年後(1972年)に、ボストン・マサチューセッツ工科大学の少壮の学者ドネラ・H・メドウズさんがまとめた報告書が『ローマクラブ』によって発表されました。
『成長の限界 — ローマ・クラブ「人類の危機」レポート— 』と題する報告書は、人口増加や環境悪化などの現在の状況が続けば、21世紀には地球上の成長は、限界に達することを予測するものでした。そして、この地球の破局を避けるためには、それまでの成長一辺倒のあり方から、世界的な均衡をはかることの必要性が示されました。
この報告書によって、私たちは迫り来る危機の「時間の問題」に気づくことができました。今、これ以上成長してよいと、だれが言えるでしょう。この報告書が発表されたとき、メドウスさんは30歳でした。30歳の女性が、この報告書をまとめたことに、今更ながら感動を覚えます。
彼女はこの後、20年間にわたってバラトングループという集いを主宰し、毎年、ハンガリーの保養地バラトン湖畔に集い合って議論をする場を設けました。
この集いに参加する科学者は、自国の石を1個持参し、それをテーブルに並べて議論しました。地球の各地からやってきた科学者は、議論の結果を自国に持ち帰って実践し、大きな成果を挙げています。
名著『複合汚染』で有吉佐和子さんが書いたこと

有吉佐和子
ありよしさわこ
1931—1984年
(日本の小説家、劇作家、演出家)
和歌山県和歌山市生まれ。
『華岡青洲の妻』『香華』『紀ノ川』『恍惚の人』『三婆』など、日本の歴史や古典芸能から現代の社会問題まで、多分野にわたり長期間の綿密な取材に基づいた作品を次々に発表、数多くのベストセラー小説を生み出した。
複合汚染とは、2種類以上の汚染物質が結合して、人の健康や生活環境に相乗的に影響を及ぼすことをいいます。有吉佐和子さんは、さまざまな毒性物質の複合汚染の実態とそれを生み出す構造について、実に丹念に調べあげ、緻密な文章によって書き上げました。
それにしても、『紀ノ川』や『華岡青洲の妻』で知られる人気作家がなにゆえに告発的な文章を書いたのか、当時大きな話題となりました。
当時「あれは文学とはいえない」という批評も少なくありませんでした。そうした批評に対し、文芸評論家の奥野健男さんは文庫本の解説で「およそ小説の常識からかけはなれている作品である」「『複合汚染』は、間違いなく文学作品である」「この作品から受ける感銘は、まさに文学的感銘にほかならない」と言い切りました。
奥野さんは「ある文芸雑誌の名物的な元編集者が、『有吉佐和子がついに純文学を書いた。『複合汚染』こそ、おれの考えている純文学の極致だ』と感動的に語った」エピソードを紹介しています。
また、京都の漬物屋の主人が、毒を売ってまで儲けたくはないと、20年も前から防腐剤を用いず、商売を縮小してまで昔どおりの安全な製法にこだわり続けている逸話も文中で紹介しています。レーチェル・カーソンよりも前に、そんな漬物屋がいたことの感銘は深いものがあります。
(『住まいを予防医学する本(2007年発行・町の工務店ネット)』第一章より)
ヒポクラテスは、「健康とは生命現象の連続性であって、その障害が病気」だといっています。現象の連続性そのものが生命でもあります。連続性を無視した暮らしや社会はどこかに歪みが出てきます。どこか近視眼的、反射的な対応が目に付く昨今の社会ですが、「びお」は、原点に立ち返えり、暮らしと生命をもっと考えていきたいと考えております。





