
暮らしの時代
美術・デザイン・建築 –– 味岡伸太郎の仕事
Vol.3 手仕事であることの意味
使いたい文字をつくる
味岡伸太郎の活動範囲は美術のみならず、グラフィックデザインを中心に、建築・家具、出版活動など、多岐にわたる。
中でも知られているのは、文字=書体のデザインだろう。
グラフィックデザイナーなら、「小町」「良寛」という仮名書体を一度は目にしたことがあるはずだ。
一般的に知られる明朝体よりも筆文字のニュアンスが強く、文字を組むだけでデザインが十分に成り立つほど。実に使いやすい書体だ。
それは、味岡が文字を、グラフィックデザインでもっとも重要な要素として考えていることが大きく作用している。
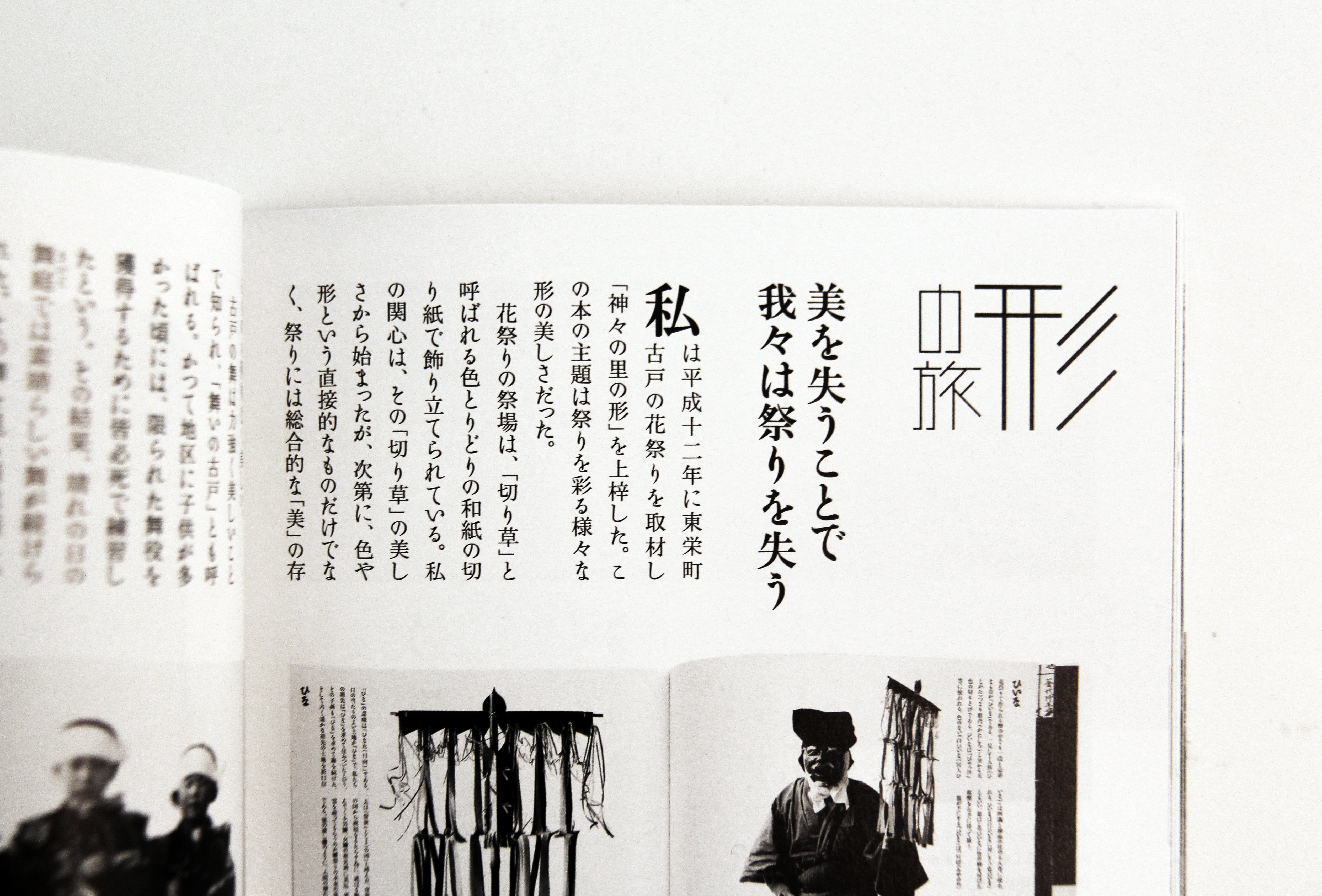
味岡が手がける出版物は、すべて味岡本人がデザインした書体を用いている。
書体を自分でつくったのも、デザインの中で短歌を組もうとした際、短歌に適した書体が見つからず「ならば自分で」と思ったのがきっかけ。
文字を“つくりたい”のではなく“使いたい”が先にあったのだ。
味岡は文字とデザインの関係について、こう語る。
「デザインの目的はコミュニケーション。ビジュアルもその手段の一つですが最終的にメッセージを伝えるには文字が大事です。しかし今のフォントはいいものがないですよ。
一番問題なのは、文字をつくる人が、すなわち使う人じゃないこと。つくりたいものじゃなくて使いたい文字をつくってほしい。だから自分でつくったんです。むしろ本当に責任をもっていいものをつくるには、文字だって自分で書くのが当たり前だと思うのですが」。
グラフィックデザイナーにとっては、既成の書体を選ぶのではなく、自らデザインできることも大事な資質の一つであると、味岡は説くのだ。
そこで浮かび上がってくるのが、“手仕事”というキーワードである。
手に宿る知性
考えてみれば、味岡の仕事は、全て手仕事の延長上にあるといっていい。
美術はもちろん、グラフィックデザインも、つい十数年前、コンピューターが本格的に導入されるまでは誰もが手作業。題字や本文で文字の間隔を詰める作業は、その最たるものである。
建築もそうだ。
味岡が建築や家具に関わるようになったのは、’80年代末、全てのデザインを担当していた和洋菓子の老舗・入河屋(静岡)から、頼める人がいないと言われて店舗の設計に携わったのがきっかけ。設計事務所との協同で、商業施設から戸建て住宅、集合住宅まで幅広く手がけてきた。
当初は鉄骨造や鉄筋コンクリート造が多かったが、近年は木造が中心に。選ぶ素材も自然素材が多くなり、住宅の外壁仕上げは下見板張りが多い。
「鉄骨造は規格品の範囲でしかできないし、鉄工所もビジネスライクで、色んな意味で融通が利かない。その点、木造だったら、質感も全然違うし、優秀な大工さんに巡り会えば、手仕事の延長でできるのがいい」。

和洋菓子の老舗・入河屋 豊橋湊町店。(写真提供=味岡伸太郎)
さらに、こう続ける。
「照明器具にしても家具にしても、人のデザインを入れるのではなく、自分でつくればいいじゃないかと。優秀な建築家は自分でつくってますよね。腰掛けひとつをとっても、ちゃんと身体感覚を把握しなければつくれないものね。どうも目の前のことを身体感覚で処理できる力が、欠けてるような気がします」。
手仕事と使う側の感覚を大事にしてきた味岡にとって、現在の建築の状況は違和感があるようだ。
そこで思い出すのは、イタリアの建築家で批評家のアンドレア・ボッコが提唱する「手の知性」である。アンドレアは、北イタリアの山村で自然と共存してきた住宅群を調査する中で、かつての手仕事が持ちながら、現代技術の普及で失われていった、技術・生活・生産を横断する知性を感じたという。それが「手の知性」だ。
味岡の仕事にも、手仕事ならではの身体感覚や実用性を兼ね備えた何かが宿っている。それを一言で表すならば、“美”ではないだろうか。
(続く)
表題写真提供=味岡伸太郎
写真(特記以外)=中村謙太郎
