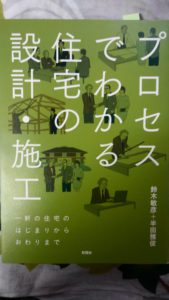味岡伸太郎展 富士山麓20景
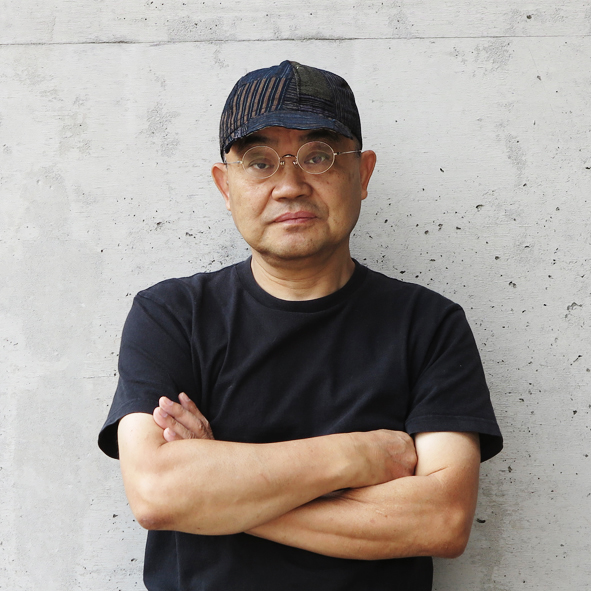
あいちトリエンナーレ2016で、味岡伸太郎さんの作品はご覧になりましたか?
土に魅せられ、土を画材として絵を描く味岡伸太郎さんの個展が11月に、東京と豊橋で開催されます。

富士山麓の20か所で土を採取、
東京側の5か所で採取した土で描いた絵を、東京で「富士山麓20景之内五」として
愛知側の15か所で採取した土で描いた絵を、豊橋で「富士山麓20景之内十五」として
展示します。
東京
RED AND BLUE GALLERY
東京都中央区新富1-5-5トーア新富マンション102
11月10日(金)-12月9日(土)
火~金 12:00-19:00/土 12:00-18:00/日・祝・月休廊
11月10日(金)17時よりトークショー&オープニングパーティ。
豊橋
Gallery SINCERITE
愛知県豊橋市向山大池町18-11
11月3日(金)-26日(火)11:00-18:00 水曜休廊
11月3日(金)15時よりトークセッション&オープニングパーティ。[味岡伸太郎と土と絵画]味岡伸太郎×櫻井拓(ART CRITIQUE)
◊ 味岡伸太郎さんによる町角シートもあります。
Vol.5 町角シート 味岡伸太郎 花頌抄 1