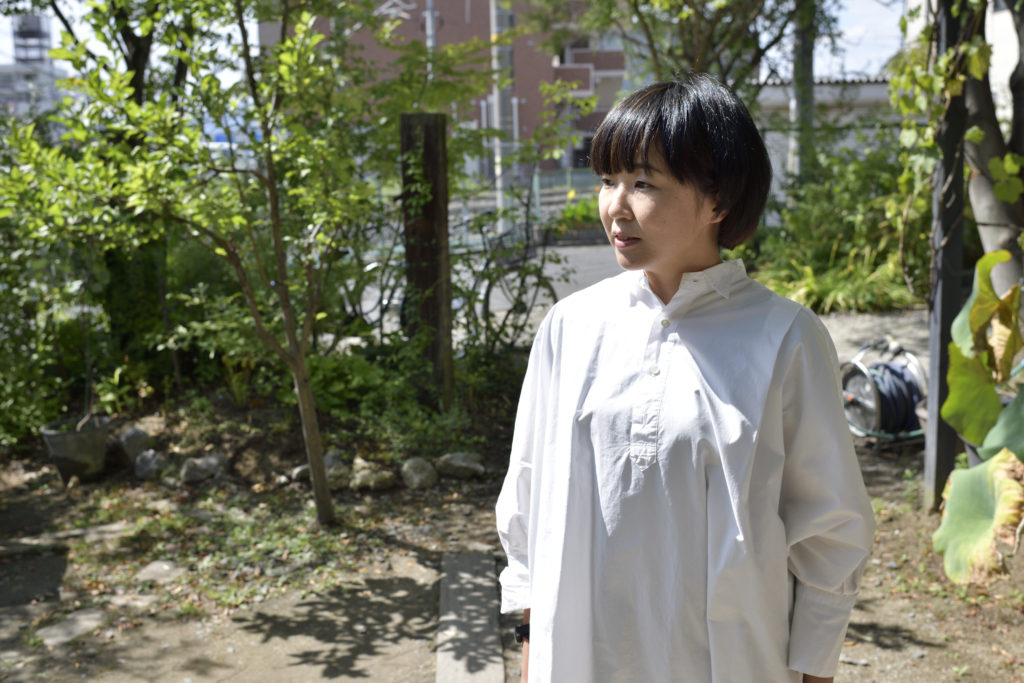
暮らしを教えてくれたひと
住まいだけでなく、店舗、アトリエなど、そこで日々暮らす人たちの凝らす工夫は、住まいの設計をするうえで大きな手がかりになることがあります。愛媛県で建築設計を営む福岡美穂さんは、これまでに“暮らし”をテーマに活躍する達人たちの仕事から、設計の着想を得てきたと言います。このシリーズでは、福岡さんが“暮らしの達人”を訪ね、その根底にある考え方や信念をインタビューすることで、暮らしを設計するとは何か、考えるヒントを探しに出かけます。
Vol.4 取材を終えて
「くるみの木」を訪れたとき、この空間に設計事務所があったら面白いのでは、との着想を浮かべ、「暮らし」そのものを主体化した設計室のイメージを温めながら「暮らしの設計室」を立ち上げたという福岡美穂さん。今回、「くるみの木」を主宰される石村由起子さんにはじめてインタビューするなかで、どんなことを感じたのでしょうか。取材をふりかえります。
石村さんの「ぶれないモノサシ」って、何からできているのだろう。
6年前、初めて講演会でお話を聞き、走り続ける強さに魅せられました。住宅設計に携わるなかでも、割と高い確率で「奈良くるみの木」をご存知の方が多く、自分自身もその空間を体験したくて、「秋篠の森」に宿泊したり、はたまたクライアントとともに、松山から日帰りの弾丸ツアーで訪れたこともありました。
その柔らかく優しい空間は、石村さんというフィルターを通した、「人を喜ばせたい」という一点の信念の塊だったということを、今回のインタビューの中で思い知りました。
人を介して伝わる内在的な「心地よさ」がここには在りました。
それは、スタッフさんの自然な気遣い、何気なく飾られたオブジェ、美味しそうな匂い、美意識の行き届いた空間。そして、そこに集う作り手とお客さんにより、くるみの木を中心に大きな一体感ができているように見受けられました。
私の中での石村さんは、「真に楽しむ」ということを知っている人だと思いました。それは、「きちんとものを受け取ることができる」人とも言うのではないでしょうか。そのバックボーンには、石村さんが語った、幼少の頃おばあさんから教わった生活者としての佇まい方にあるのではないか。つまり、真に楽しむためには、日常生活の中の学びを蓄積していくことが大事であり、それがあるからこそ、初めて、きちんとものをうけとることができるのではないかと思います。それはある意味、技術とも言っていいかもしれません。
「ぶれないモノサシ」を持つ、ひとつのヒントがここにあります。
私を含め、この場所の来訪者は、くるみの木に「真に楽しむ」ための、エクササイズをしにきているのかもしれません。
