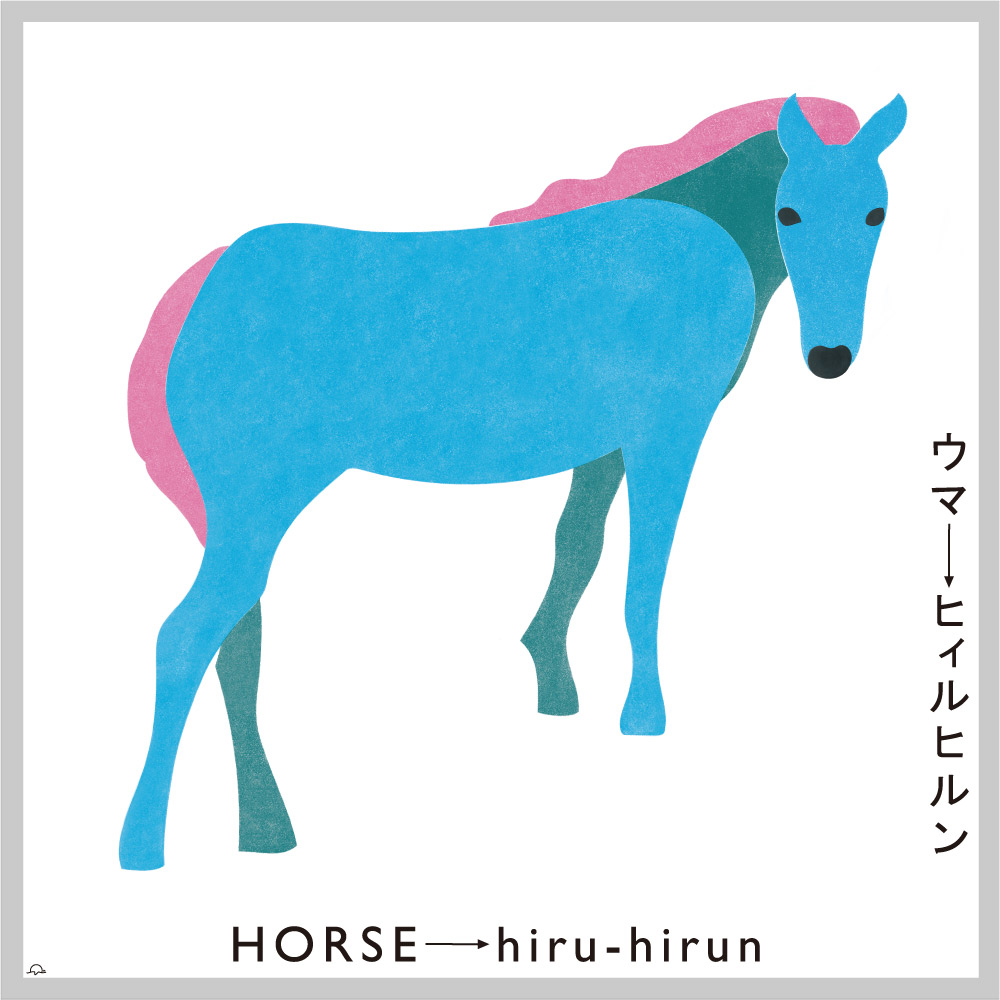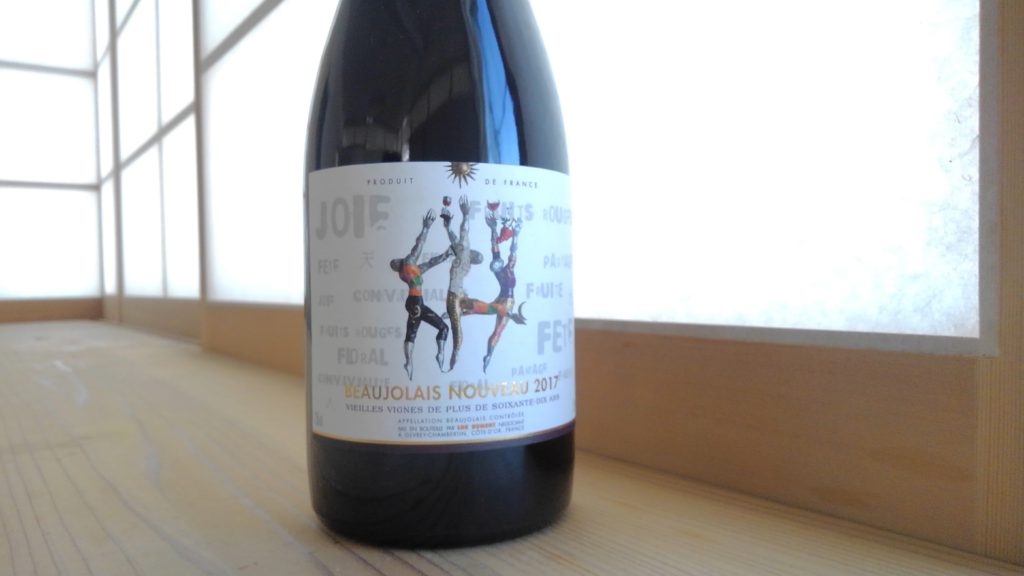2017年記事別ページビュー数ランキング・トップ10
年の暮となりました。あなたの仕事は納まりましたか?
今年の10月1日にリニューアルオープンした住まいマガジンびお。あなたのご愛読に感謝するとともに、シェアやtweetやいいね!やリンクなどさまざまなご支援に胸がポッカポカになりました。
今年の締めくくりということで、記事ごとのページビュー数トップ10を発表します(グーグル・アナリティクス調べ2017.10.01-12.28)。もちろん、トップページは除外してあります。
あなたの好きなあの記事はランクインしているでしょうか?
10位 住まいのグラフィティ Vol.3 富水の家リノベーション 徳田英和設計事務所
初期の「住まいのグラフィティ」作品。新築ではなくリノベーション作品のランクインは新しい時代を予言していますね。
9位 町角シートVol.3 町角シート 渡邉良重 Listen to me 1
9位には渡邉良重さんの町角シートがランクイン。こちらは実際のご注文も何件かいただいたと聞いております。イラストもカワイイけれど、動物の鳴き声も独特でいいですよね、ヒィルヒィルン(自画自賛)。
8位 ぐるり雑考第4回ここを離れて、次の場所へ
働き方研究家・西村佳哲さんの記事が8位に。穂高養生園のスタッフをしていた放浪のシェフの話が個人的に好きでした。
7位 町角シート誕生!
町角シートの一覧ページがこの位置に。毎日更新していた町角シートのページ、あなたはこのページで見比べて注文しましたか?
6位 びおの歳時記
このページは七十二候ごとに変わる歳時記のページです。リニューアル当初は常にトップページにあったのともう19回も更新したのでこの順位に。「木版画が彩る世界」「柿木村の一輪挿し」「四季の鳥」「季節をいただく」などの季節ごとの草木や鳥や食材の記事で構成されています。しほと太郎が季節を体験する「はじめてのこよみ暮らし」もあります。
5位 ぐるり雑考第1回違和感を手放さない
再び西村さんの記事がランクイン。西村さんと宮田識さんには8月に開催されたWebびお養成塾に講師としてお話していただきました。養成塾に参加した一期生たちは各地域で「ちいきのびお」という実を結びはじめています。
4位 ぐるり雑考第2回それがないと
再び西村さんの記事。Webびお養成塾の続編です。自分しか持っていないものをどう見つけるか、という話。
さて、これからベスト3位の発表です。ちょっと背伸びしますか、それともトイレに行きますか。それでは3位から……。
3位 ぐるり雑考第5回あいていない扉をひらく
SNSで話題になった西村さんの記事。子どもへ仕事をしている自分はどんな背中を見せられているかな、と考えさせられる話。
2位 住まいのグラフィティVol.12 鎌倉大町の家堀部安嗣建築設計事務所
第2位は工務店界隈からも、建築士界隈からも定評のある堀部安嗣さんの新作・鎌倉大町の家。螺旋階段にあこがれます。ちなみにびおソーラー搭載。
1位 住まいのグラフィティVol.1 guntû(ガンツウ) 堀部安嗣建築設計事務所
1位は堀部安嗣さんの動く住まい、ことガンツウ。10月1日の住まいマガジンびおリニューアルオープンをかざった記事でもあります。もう就航しています。
結果として堀部安嗣さんと西村佳哲さんが上位にランキングされました。来年は誰のどの記事がランキングされるでしょうか?
でも、記事の良さはページビューでは決まりません。あなたが一番好きな記事が、あなたが一番共感できた記事が、きっと一番良い記事なのではないでしょうか。
さて、あなたのランキング1位の記事は何ですか?(甲)