

- 2023年09月17日更新
仙之助編 十三の九
初めて飲んだバーボンのほろ酔いは、仙之助の心を解放し、饒舌にした。
「鯨のシーズンは終わりだというのに、どうしてホノルルに寄港されたのですが」
「強風でやられちまったマストの修理のためだ。こいつが壊れなければ、ホノルルには立ち寄らなかったよ」
「強風のおかげで私たちは再会できたのですね」
「海はさまざまな偶然の運命を船乗りに与えるものさ」
「夏は、またオホーツク海に行くのですか」
「いや、今年は北には行かない。ジャパン・グラウンドに行く。ボニン・アイランズに行かねばならない用事があるからな」
ボニン・アイランズとは、現在の小笠原諸島のことだった。
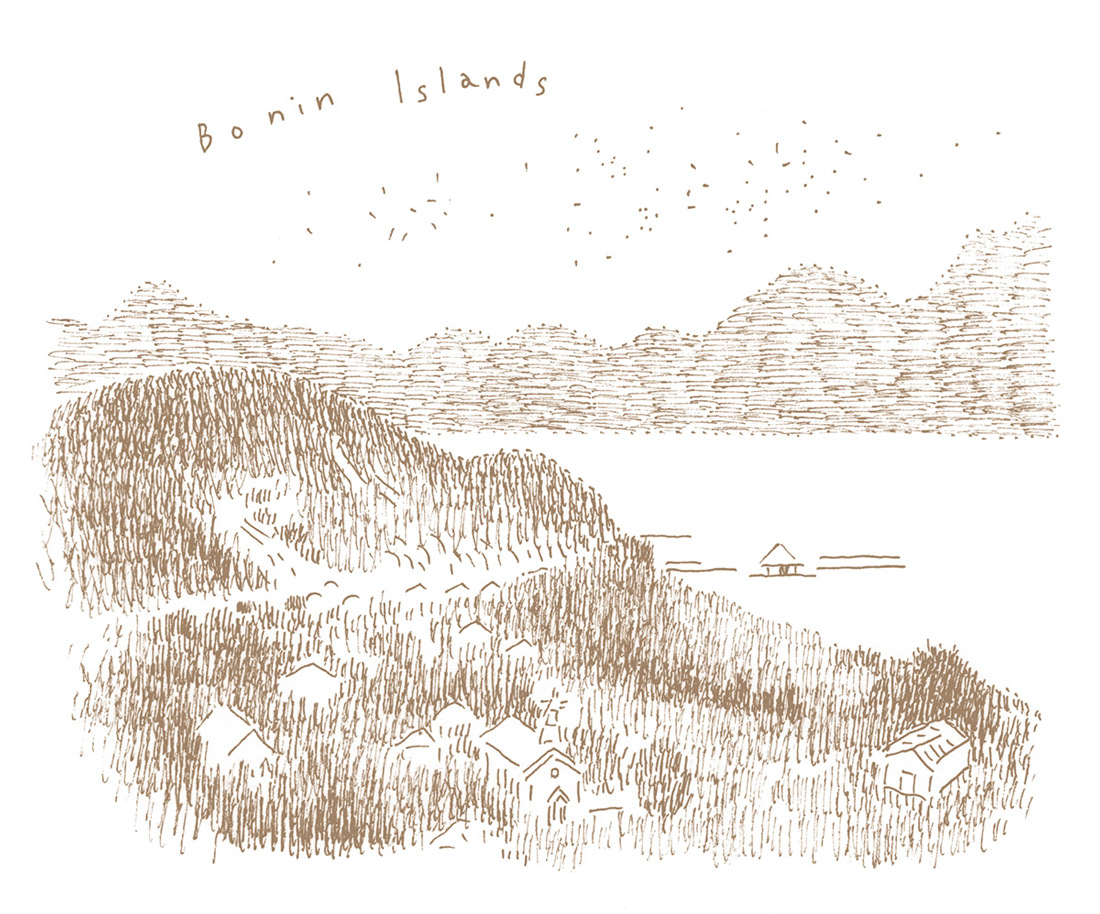
群島の名前を聞いてもぴんと来ていない仙之助にダニエル船長は可笑しそうに言った。
「ペリー総督が初めて日本に向かった時も立ち寄っている。日本が開国に応じなかったから、ボニン・アイランズを捕鯨船の補給基地にしようとしたらしい。そうそう、お前が尊敬するジョンマンも、何年か前に、日本で捕鯨事業を立ち上げようとして、このあたりを航海していたと噂を聞いたことがある。お前は知らないのか」
「知りませんでした。私はジョン万次郎の英語の教本で学んだだけですから」
「ハハハハ、ジョンマンの本質は、鯨捕りだからな。ジャパン・グラウンドに目をつけた才覚こそ、尊敬しなければならないぞ」
「はい。ボニン・アイランズはアメリカの島なのですか」
「いや、違う。お前の国の島だろう。だが、村の長老は、ナサニエル・セヴォリーというアメリカ人だ。ジョンマンや俺たちと同じ、マサチューセッツの出身だと聞いている」
「日本の島なのに、長老はアメリカ人なのですか」
「ああ、面白い島だろう。そのナサニエルにホノルルと手紙のやりとりを頼まれてきた」
「手紙を渡したら、その後はどこに向かうのですか」
「ジャパン・グラウンドでしこたま鯨を捕るさ。そして……、また横浜に向かうかな」
「横浜……、本当ですか?」
「故郷に帰りたいのか」
「故郷が恋しいのではありません。でも、移民の帰還が本決まりになったら、彼らには新しい旅券が用意されるでしょうが、私には立場がありません」
「そうか。クレマチス号のマストの修理には、まだ少し時間がかかる。それまでに決めれば良い。俺は、お前とまた航海できるのは大歓迎だ」
「ありがとうございます」
隣でじっと二人の会話を聞いていたウィルがぽつんと言った。
「こんなに役に立つスクールボーイに辞められるのは本意じゃないが、お前の人生だ。お前が決めればいい。ずっとハワイにいたければ、その場合は俺がなんとかしてやる」
