

- 2019年04月07日更新
- 画 しゅんしゅん
一の十一
父祐司が、突然現れた親戚、虎造の話を私にしてくれたのは、それからしばらく経った夏休みだった。
私は高校一年生だった。
箱根から上京して、東京の原宿にあった女子大生向けの学生寮で暮らし始めていた。新しい生活が始まった夏だった。
箱根で通っていたミッションスクールは高校まであったが、東京の高校を受験することを決めたのは、自分をとりまく環境から逃げ出したい衝動があったからかもしれない。
戦争中、東京の九段にある本校の疎開学園として発足した箱根のミッションスクールは、母の裕子も卒業生だった。そればかりではない。仙之助の娘たち、孝子、貞子、美香も戦前、九段の本校を卒業していた。当たり前のように入学させられた学校を忌み嫌っていたのは、校則の厳しさもあったけれど、自分をとりまく世界から逃避したい願望ゆえだったのだろう。
逃げようとした対象が家だったのか、富士屋ホテルだったのか、箱根という土地だったのかはわからない。なぜならそれらは、渾然一体としたものだったからだ。
私たち家族は、家族としてまとまる以前に、ひとりひとりが強いシンパシーと共に富士屋ホテルにつながり、結果、全体として家族の呈を成していた。
真ん中に存在する富士屋は、家業というより、もはや得体の知れない生命体のようだった。だから、富士屋ホテルの経営が山口家を離れた後、そうした家族のつながりまでもが、ボロボロと空中分解していくような感覚を幼心に感じたのだった。どうして、たかがホテルにそれほどまでに翻弄されるのか。疑問に思う余地もないほど、私たち家族の中心に富士屋ホテルがあった。
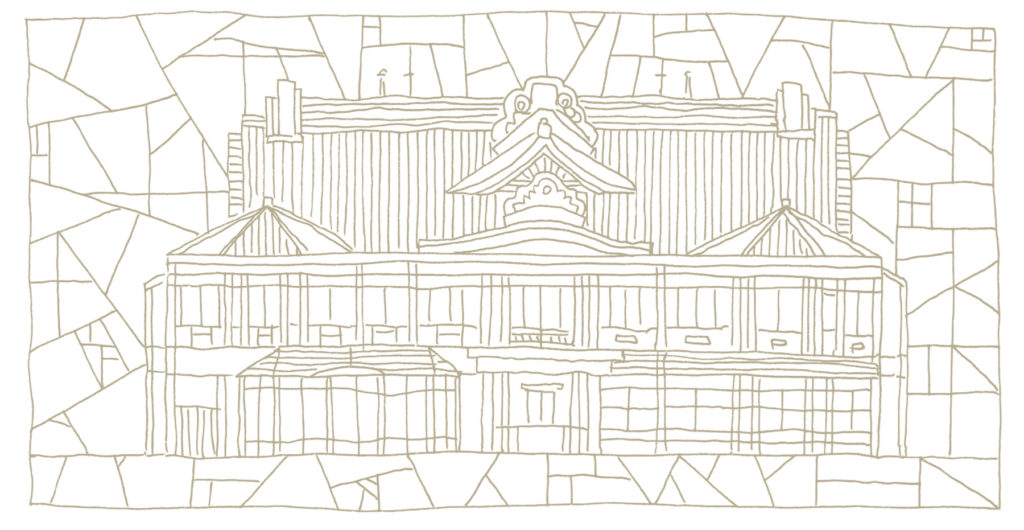
母裕子は、富士屋ホテルが山口家の経営を離れ、祖父堅吉が亡くなった頃から心身の均衡を失い始めた。
きっかけは慢性膵炎を患ったことだった。
アルコールと脂肪分の多い食事が引き金となる発作は、耐えがたいほどの激痛を伴う。やがて彼女は、痛みをとるために処方された鎮痛薬の依存症に陥っていった。それでも彼女は、節制をせず、酒と美食におぼれては発作をおこした。そのことが、子供心にも母親に対する同情を剥いでいった。
拮抗性鎮痛剤のソセゴンという薬品名は、今も胸のざわつくような感覚と共に私の記憶に鋭く刻まれている。
「ソセゴン、ソセゴン」
母親の面影を辿ろうとすると、狂ったように薬を求めたこの声に行き着いてしまう。ワインボトルに詰めて持参した富士屋ホテルのコンソメスープが、もっぱら食事制限された時の食事で、ブイヨンの馥郁とした香りと注射液の匂いが混じった、こもったような空気が病室に充満していた。壊れた彼女の心身と富士屋ホテルが一体となった匂いを、私は今もありありと覚えている。
受験を決めた中学三年からの一年間は、とりわけ入退院を繰り返し、自殺未遂まで図った。
私が逃げ出したかったのは、そうした混沌、そのものでもあったのかもしれない。
