

- 2019年02月19日更新
- 画 しゅんしゅん
一の二
私が富士屋ホテルを「物語」として意識するきっかけになる出来事があったのは、母の裕子が亡くなった年のことだ。
あの出来事がなければ、私は、富士屋ホテルを体の一部のように思ったまま、富士屋ホテルとは関係のない人生を歩んでいたに違いない。
ずっと後になってから、裕子が亡くなった年は富士屋ホテルが創業百年の節目であったことに気づかされた。
長く気づかずにいたのは、ホテルが百周年を祝わなかったからである。歴史を振りかえると、八十周年と百十周年は盛大に祝っていて、少しちぐはぐなことになっている。
その八年前、経営が山口家の手を離れたことが理由だったのだろうと推測する。創業家との立ち位置が、まだ上手く整理できていなくて、百周年は見送られたのかもしれない。
祖父堅吉は、創業者仙之助の次女、貞子の婿だった。彼女は、三九歳の若さで亡くなり、後妻となった千代子が裕子の母、すなわち私の祖母になる。貞子にまとわりついた不吉な死の影は、不気味な符合となって次の世代まで続いた。裕子が亡くなったのも同じ三九歳だったのである。
裕子の婿として迎えられたのが父の祐司である。
祐司は、同族経営が終わってからもホテルに残り、努力して頭角をあらわし、総支配人になった。
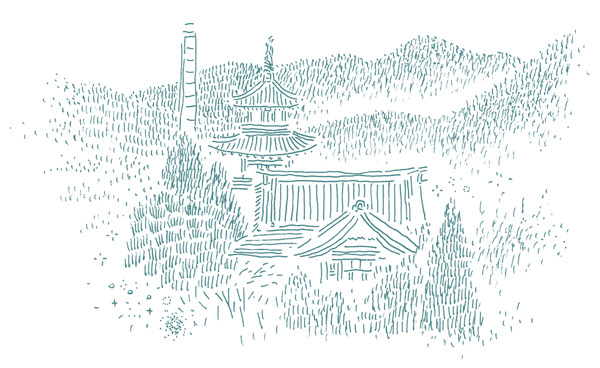
八年の間におきた経緯を知らない者は、山口の名前を継ぐ祐司がいることで、同族会社であるまま、富士屋ホテルの歴史が継続していると勘違いした。新経営者と上手く渡り合いながら、総支配人兼社長であった堅吉にならい、彼を「社長」と呼ぶ古い顧客には、あえて勘違いを否定せず、一方、本当の社長には忠義をつくした。そうした如才なさが祐司にはあった。
あの日の山口虎造も、きっとそうだったに違いない。
だからこそ、彼は安心して、初対面の祐司に一族の出自を話したのだと思う。
富士屋ホテルが百年の節目を迎えた年の梅雨明け間際、乳白色の霧が谷底を包んだ朝のことだった。出社してまもなく、祐司は、ベルマンから伝言を受けた。夏が近いことを感じさせないほど、湿気を帯びた空気がひんやりとした梅雨寒の日であった。
「山口家のご親戚とおっしゃる方が玄関にお見えです」
「おかしいな。今日、どなたかいらっしゃるとは聞いていないな。お名前は伺ったのか」
「はい、山口虎造様とおっしゃいます」
「虎造?」
「はい」
同じ山口姓だったので、不思議にも思わなかったのだろう。
