

- 2020年11月01日更新
- 画 しゅんしゅん
仙之助編 二の二
一八六〇(万延元)年六月四日、横浜は開港二周年を祝う山車や芸者の手踊りが繰り出して、お祭り騒ぎとなった。
山口粂蔵が仙之助との養子縁組を急いだのは、その日を共に祝いたい気持ちがあったからだ。前年の開港した日の横浜はまだ何もなく、何の祝賀も行われなかった。たった一年で横浜は大きく変わった。この先、どれほど発展するかわからない。
粂蔵にとっても横浜は故郷ではない。未知なる可能性を信じてやってきた新天地だった。ここに根づけば、いくらも大きな成功が掴めるに違いない。そのことを仙之助にも実感させたかった。
大浪家では、母親だけが突然の出来事に戸惑っていたが、仙之助は、不思議なくらい生家を離れる躊躇や感傷を見せなかった。少年の見知らぬ世界へのただならぬ好奇心を粂蔵は好ましく思った。
父親の大浪昌随が粂蔵に望んだのは、仙之助に学問をさせることだった。粂蔵は、養子に迎えた後は江戸の漢学塾に通わせることを約束した。
大曽根村から横浜までの道のりは、旅というほどの距離でもなかったが、仙之助には見知らぬ異国に旅立つような高揚感があった。
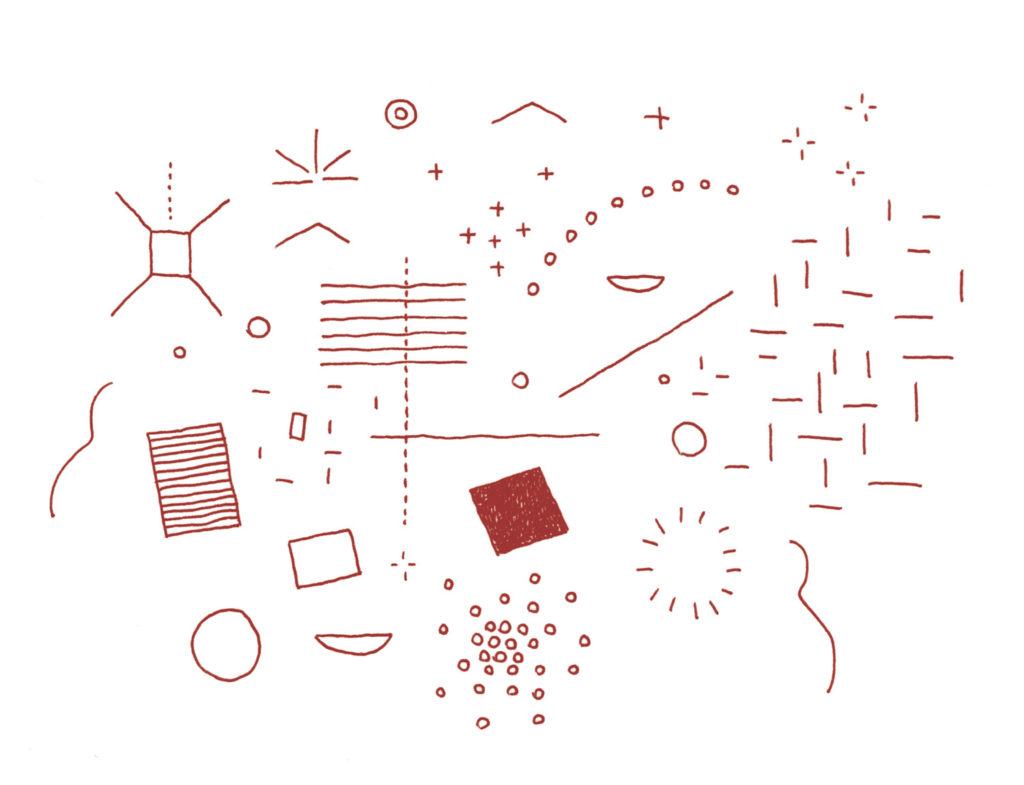
粂蔵が自分の商売について仙之助に話したのは、その道すがらのことだ。
「開港地には、まずはともかく必要なものがある」
「何でしょうか。船に積み込む薪や水ですか」
「賢いな。だが、それだけではない」
「商人ですか」
「そうだな。横浜には開港してすぐ異国の商社が店開きをした。商人たちは成功を夢見る若くて血気盛んな男たちだ。横浜にはまだ異人の女はほとんどおらぬ」
「……」
「男というものは、さみしがり屋だからな」
「……飯盛り女ですか」
年端もいかない漢方医の五男坊だったが、ませたところがあると思った直感は当たったと粂蔵は思った。飯盛り女とは、宿場で一晩の相手をする女のことだった。
「というか、吉原だな。わかるか?」
「はい、極楽浄土のようなところだと聞いたことがございます」
「そうか、そうか」
粂蔵は笑いながら仙之助の頭をなでた。
「開港してすぐ幕府は横浜にも吉原をこしらえたのさ。わしはそこで伊勢楼という店を開いた。今は岩亀楼という大店が異人の商売を独り占めしているが、こっそり来る異人もおる。そのうち横浜に来る異人がみんなこぞって来る店にするつもりだ」
横浜の吉原とは、港崎遊郭のことだった。
