

- 2023年09月24日更新
仙之助編 十三の十
ダニエル船長との再会からほどなくして、仙之助はクレマチス号に乗船することに決めた。このままハワイにとどまっていても、もはや仙之助の役目はないと判断したからだった。
富三郎は、一刻も早い移民の帰国に奔走している。おそらく、遠くない将来に彼の交渉は実現するだろう。そうなった時、密航者である仙之助は役にたつどころか、足を引っ張る存在であり、自分自身の身の上にも危険がおよぶ。
密航者として出国した以上は、密航者として帰国するしかない。
一八六〇年代の太平洋において、それを可能にする唯一の手段が、捕鯨船なのだった。
決意を聞いた富三郎は、何も言わずにうなずいた。
仙之助は富三郎に伝えたい思いは山ほどあったが、ユージン・ヴァン・リードを巡る葛藤が、言葉にすることを躊躇させた。
クレマチス号のマストの修理は予定より早く終わり、出港の日を迎えた。
ただひとり、ウィル・ダイヤモンドが桟橋に見送りに来てくれた。
仙之助を強く抱擁すると、耳元で言った。
「お前と会えて、うれしかった。達者でいろよ」
「私もお会いできてうれしかったです。いつかまた……」
と言いかけて、再会は限りなくあり得ないことと悟って言葉を飲み込んだ。
次の瞬間、ふいに涙がこぼれそうになって掌で目をこすった。
密航者を乗せた捕鯨船は、夜明け前の静寂のなか、桟橋を離れた。
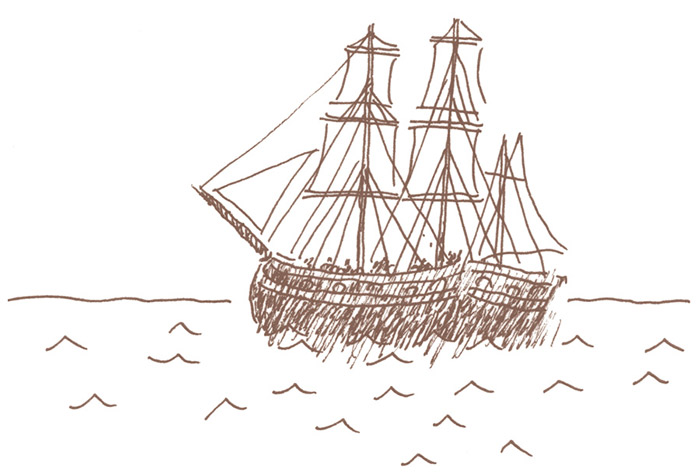
ホノルルに入港した時と同じく、仙之助はダニエル船長の指示で船底のキャビンにとめおかれた。今一度、ホノルルの風景を脳裏に焼き付けたいと思ったが、仕方なかった。
「コノヨノゴクラクジョウド……」
ハワイへの惜別の思いから仙之助は、ヴァン・リードの口癖を独りつぶやいた。
現実のハワイは、美しくもあり、矛盾にも満ちていた。
それでも花と緑の香りを含んだ風の心地よさだけは、極楽浄土と呼ぶべきものだった。
仙之助の脳裏に、ラニの家で体験した宴のシーンが甦る。
夢とも現とも知れない宵に見た風景もまた、まさにこの世の極楽浄土だった。
とりわけ禁断の踊りの優雅さと妖艶さは忘れることができない。
だが、ここで仲間の命が失われたのも、また事実だった。悲劇がことさらに悲しく、せつなく胸に迫るのは、ここが美しい島だからに他ならなかった。
「おおい、港を出たぞ」
顔馴染みの船員がキャビンの扉をノックした。
デッキに出ると、朝陽を浴びて真っ青な大海原が広がっていた。
振り返ると、ホノルルの市街地はすっかり遠くに去り、何度となく山道を越えたコウラウ山脈の山並みが島影のシルエットを形づくっていた。
また、捕鯨船の冒険が始まる。仙之助は武者震いを抑えられなかった。
