

- 2019年09月29日更新
- 画 しゅんしゅん
二の十二
「冒険商人?」
「さよう。長崎のグラバーなんぞが、よくそう呼ばれます。鎖国時代の日本は神秘の国でしたから。いや、欧米からしたら、東洋すべてが神秘だったんでしょう。そうした国々に赴き、商売をすることで、一攫千金を夢見た者たちのことです。まあ、コリアーもその類だったんでしょうな」
「わくわくするような呼び名ですね」
「アメリカは面白い国でね、幕末の頃、冒険商人を国を代表する領事のような職につけたんです。ハリスも海を渡り、東洋にやってきた冒険商人だったんですよ。イギリスは、そんなことはしないで、ちゃんと本国からエリートを送り込んできたから、グラバーは政治に関われなかったんですな。あの男は、政治に首をつっこみたい野望があったのにね。コリアーももう少し早く生まれていたら、歴史に名前を刻んでいたかもしれんね。そういえば、ハリスもコリアーと同じニューヨーク生まれだったそうですよ」
「虎造さんにも、その血が流れているんですね」
「ははは、そうだね。若い頃にはずいぶんやんちゃもしたけれど、今思えば、コリアーの血だったのかもしれんね」
悪戯っ子のような表情で、虎造は笑った。
祐司は、デザートにレモンパイをすすめた。
レモン風味のカスタードの上にメレンゲを載せた、爽やかな味のパイは、富士屋ホテルに昔からある菓子のひとつだった。アップルパイも有名だが、色合いも華やかなレモンパイの方が、手土産にしても喜ばれることが多かった。
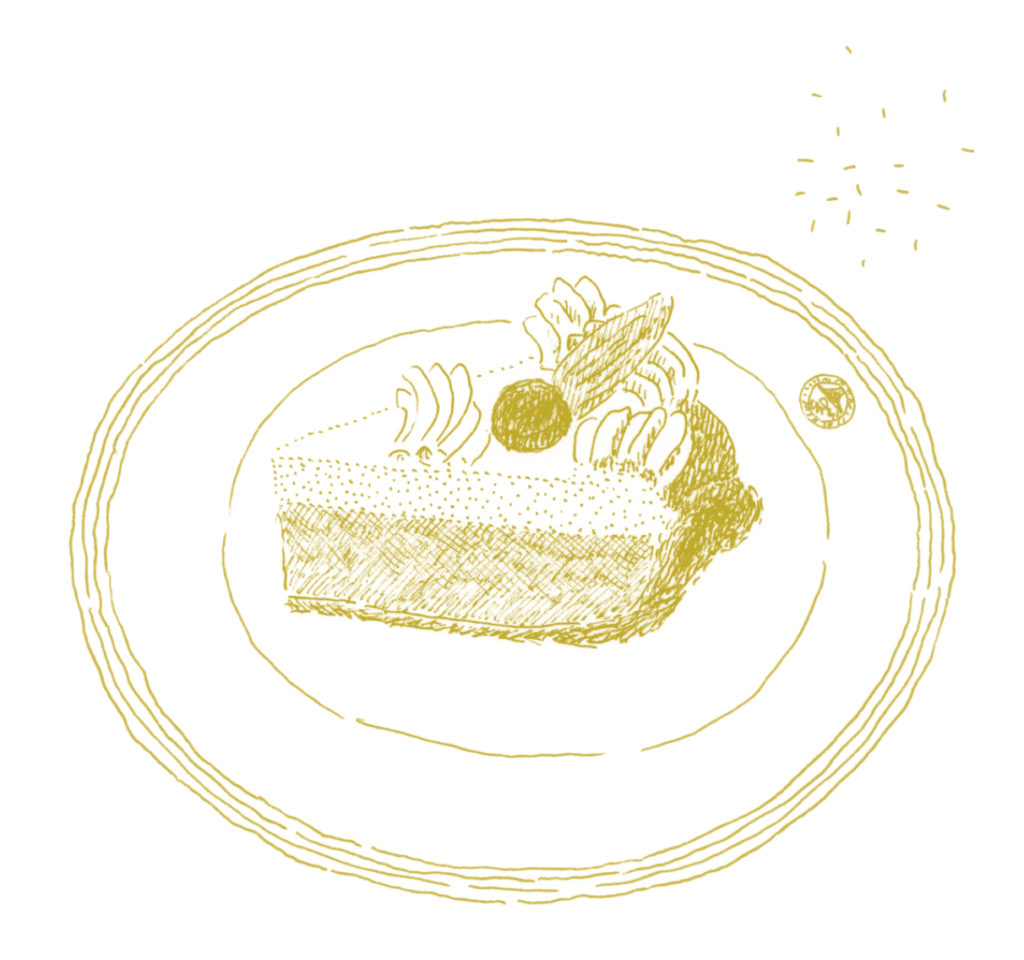
食後のコーヒーを飲みながら、虎造は、またひとしきり天井を見上げて、感慨深げに言った。
「ここもまた、海を渡ってきた外国人にひととき、東洋の夢を見させようとしたんでしょうな」
「神風楼と同じに、ですね」
祐司は言葉をつないだ。
「いや、そちらから言われては恐縮ですな」
「仙之助も正造も若い頃に単身海を渡っています。彼らも冒険商人の心を持っていたんでしょう」
「そうかもしれんね。いや、今日は、大変な歓待で、恐縮でした。今度は、横浜でお目にかかりましょう。本覚寺の墓にご案内しないといけませんな。こんなご馳走はできませんが、山口家の墓だけは、なかなか立派なものですよ。今はもう神風楼はありませんがね、墓にだけは、その名前が刻まれております」
