

- 2020年03月01日更新
- 画 しゅんしゅん
三の九
大学二年になった時、編集プロダクションのアルバイトを始めたのは、無理矢理にでも書く仕事を始めたいと思ったからだ。
大学を卒業したのは、男女雇用機会均等法が施行される前年で、私は第一志望だった新聞社の入社試験に失敗した。TV局系列の通信販売会社に就職したが、仕事になじめかった。
配属されたのはテレビショッピングの部署で、宝石貴金属担当のアシスタントになった。親会社のTV局が人気を独占していた時代のことで、お笑い番組の着ぐるみが片隅においてあるスタジオで、ダイヤモンドや金を売っていた。
入社した年の夏、大きな航空機事故があった。
そのニュースが報じられるスタジオで、金のネックレスを売ったことはよく覚えている。テレビショッピングのコーナーがある情報番組は、報道特番にとってかわられたが、墜落した機体の発見は午後で、午前中は何も動きがなかった。空いた時間に紹介した金のネックレスはとてつもなくよく売れた。番組の視聴率が高かったからだ。TV画面に事故機の凄惨な画像が映し出されても、受注センターの電話は鳴り止まなくて、人の心の不思議さを思った。
私が、ここは自分の居場所じゃないと感じた瞬間だった。
ジャーナリストとしての衝動に突き動かされたのかどうかはわからない。だが、目の前にある金のネックレスと、TV画面の事故現場とのコントラストが、私の心を再び揺さぶったのだった。
就職を失敗した時に思考停止していた何かが動き始めた。
私は一年半ほどで退社すると、学生時代のアルバイトの経験を頼りにフリーライターとして独立した。
やがてバブル景気がやってきて、海外旅行ブームが訪れた。
若く実績がなくとも、海外取材の仕事がごろごろ転がっている時代だった。気がつけば、ホテルの取材をするようになっていた。
私は、無署名の地味な原稿を山のように書いた。海外の高級ホテルに取材に行くこともあり、景気の良さは待遇の良さにあらわれたけれど、B2の鉛筆で原稿用紙のマスを埋めている間に、バブル景気は過ぎ去った。
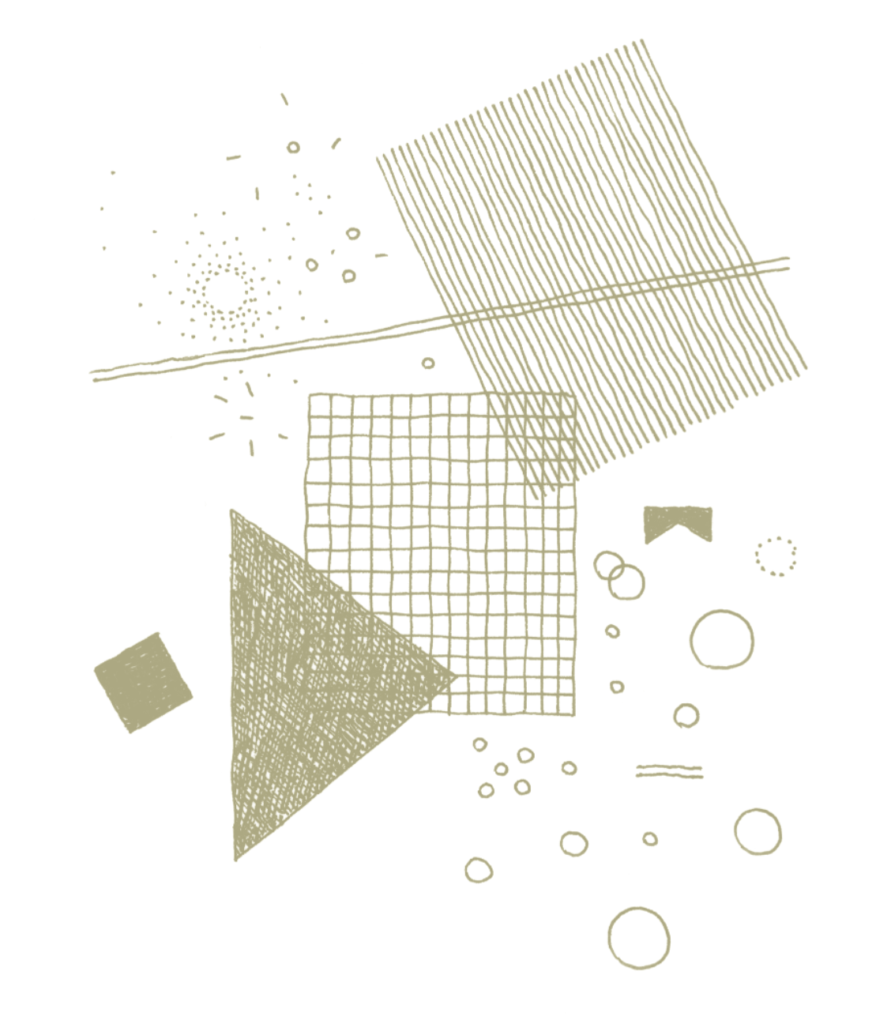
淡々と仕事をする日々が続き、初めての単行本を出版する機会が巡ってきたのは、私が三一歳になった年のことだった。
一九九〇年代は、若い女性がこぞって海外に出かけた時代だった。最初の企画は、若い女性向けの海外旅行本だったと記憶する。
ところが、担当編集者の上司とたまたま一緒の取材旅行に行ったことから、思わぬ方向に話が展開した。
旅先で富士屋ホテルの話をしたことがきっかけだった。
南アフリカのダーバンという港町のホテルのバーでのことだ。
ネルソン・マンデラが釈放され、アパルトヘイトを定めた法律が撤廃されてまもなくの頃だった。彼が大統領に選出される一九九四年は、まだ少し先のこと。その歴史を振り返ると、あの夜がいつだったかを思い出すことができる。
