

- 2020年07月19日更新
- 画 しゅんしゅん
仙之助編 一の七
港崎遊郭の伊勢楼が新しい店を開業したのは、長州藩の若い武士たちがイギリスから密かに帰国した年のことだ。長州をめぐるきな臭い事件が続き、通訳官としてのアーネスト・サトウも仕事も増えていた。
彼が心ときめいたのは、神風楼という屋号だった。
日本書紀に「神風の伊勢の国は常世の波の敷浪の帰する国なり」という、倭姫命が天照大神から受けた神託の一説があることを彼は承知していた。
神風は伊勢の枕詞でもある。伊勢楼と神風楼とは考えたものだ。
新築の店は、玄関を入ると、すがすがしい木の香りがした。
この国では、船にしても建物にしても、木材にペンキを塗らない。無垢の木の美しさは、横浜の港で最初に小舟を見たときからサトウが魅了されたもののひとつだった。
廊下を進むと、天岩戸から光り輝く女神があらわれる様子を描いた極彩色の織物が壁にかかっていた。
「アマテラス……か?」
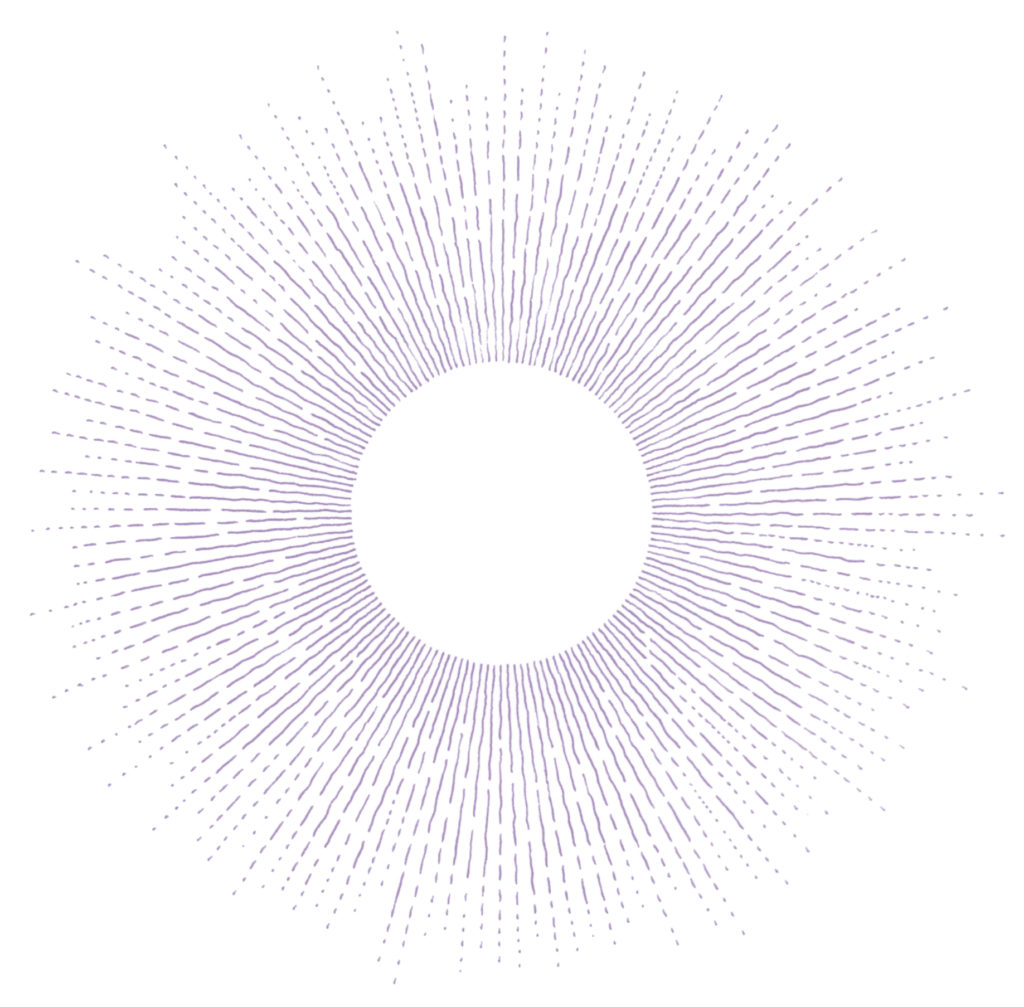
「はい、そうでございます。よくご存じで」
淡い紫色の着物をまとった女が横に立っていた。
「天照大神のご神託から名前を取るとは、恐れを知らぬにも程があるな」
「そこに登楼なさる異人さんも恐れを知りませんね」
「異人さんではない。薩道愛之助と申す」
女は小さく笑うと、黒い瞳でこちらをじっと見つめた。
「愛之助さま、フジと申します」
女はまだ笑っていた。日本名を名乗るといつものことだった。
「フジヤマのフジか?」
「いえ、花のフジでございます」
長い袖をひらりと翻すように動かした。紫の房が連なった花の模様が揺れた。
「あ、ウィステリアか」
「何とおっしゃいましたか」
「英語でフジの花のことだ」
「愛之助さまのお国にもフジは咲くのですか」
「もちろんだとも。同じように美しく咲く」
「でも、ウィステリア……と呼ぶのですね」
フジは、くるりと背を向けると何も言わず、小柄な背丈には長すぎる着物の裾をひきずりながらサトウの前を歩いた。廊下や柱は無垢の木だったが、廊下に沿って欄干がしつらえてあり、それだけは目にも鮮やかな深紅に塗られていた。ところどころに吊されたぼんぼりの淡い光に照らされる赤は、なんとも妖艶で、別世界に誘われるようだった。
