
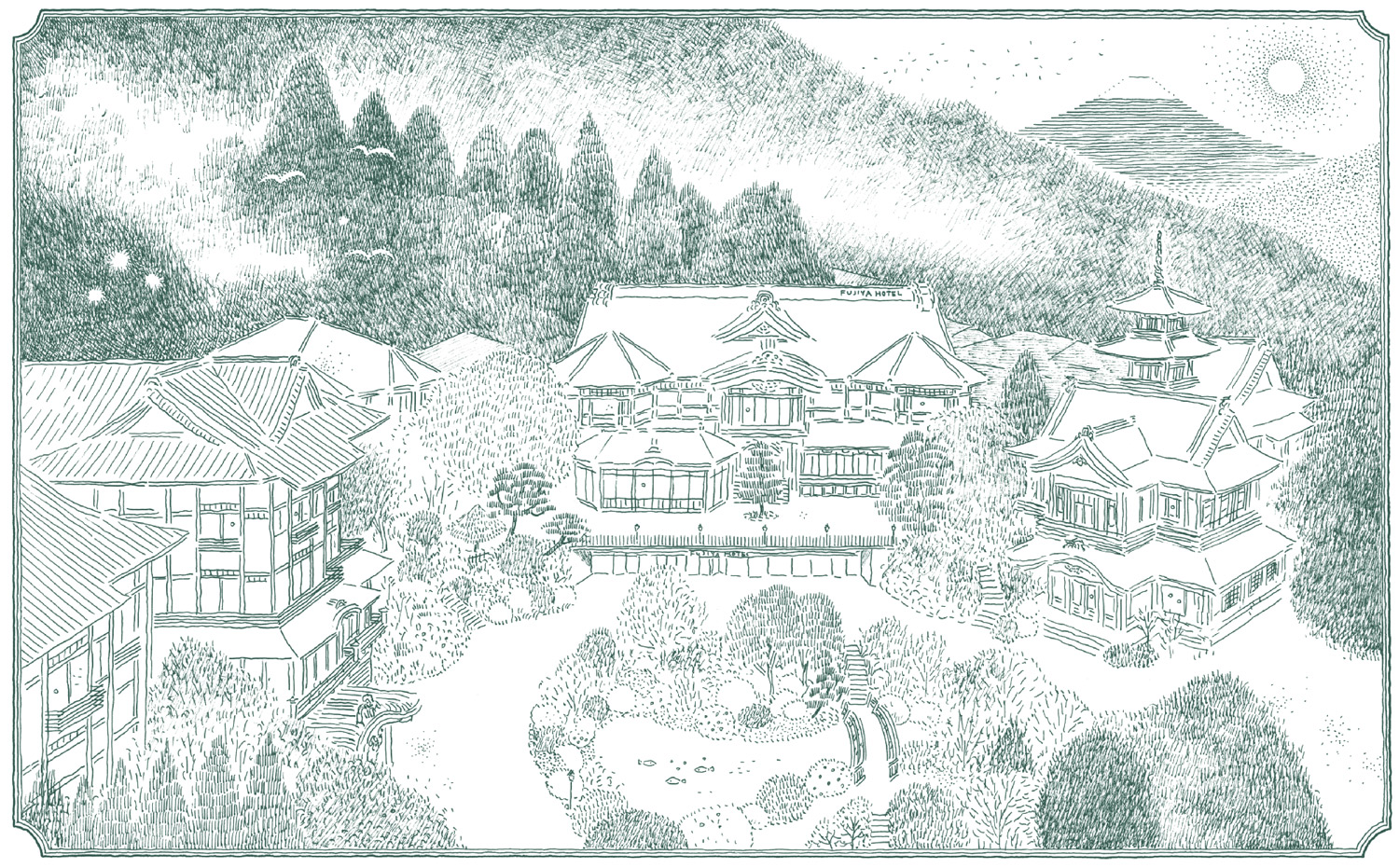
- 2025年04月13日更新
仙之助編 二十の三
一八六五年当時、テキサスの牛の価格と東部の市場で取引される牛の価格には、およそ十倍以上の差があったという。牛のロングドライブがゴールドラッシュに匹敵する一攫千金とされた理由である。
牛が集結する積み出し拠点として、最初に注目された鉄道駅は、ミズーリ州のセダリアだった。ミズーリ・パシフィック鉄道がセダリアまで延伸したことで、セントルイスや北東部の都市まで牛を運ぶことができるようになったからだ。
セダリアまでのルートは問題点も多かった。テキサス熱のために反対する農民たちの抵抗、ネイティブアメリカンの保護領における通行料などである。とりわけ人々が恐れたのは、カンザスの「ジェイホーカー」と呼ばれたゲリラだった。準州の時代、カンザスは奴隷制度を容認するかどうかで混乱したが、「ジェイホーカー」とはもともと反奴隷制の立場で闘った者たちを呼んだあだ名だった。ところが、彼らはテキサス熱の牛を阻止することを旗印に、強盗団になる者があとを絶たなかった。勝手に通行料を強要したり、牛を略奪したりして、反抗する者は容赦なく射殺した。
やがてセグリアまでのロングドライブは危険だということで、東寄りや西寄りのルートが開拓された。こうして生まれた新しいルートこそが、いわゆるカウボーイの活躍する舞台であり、牛のロングドライブの黄金時代を象徴するものとなる。
そのひとつが西部劇で知られる「チザム・トレール」である。スコットランド人の父とチェロキー族の母を持つジェシー・チザムが開発したルートだった。家畜商のジョセフ・マッコイがロングドライブのルートに使ったことで有名になった。
テキサスのサン・アントニオから続くトレールの終着点がカンザス州のアビリーンだった。言うまでもなく、カンザス・パシフィック鉄道の駅である。
マッコイはアビリーンに牛の売買ができる出荷拠点を設けることを思いつく。それまで牛で儲けようとする者は、牛を連れて鉄道で東部の都市まで行く必要があった。だが、マッコイの発案により、鉄道駅で牛を仲買人に任せることができるようになったのだ。
セグリアにとってかわって「牛の町」となったアビリーンには年を追うごとに多くの牛が集結した。最も数多くの牛が集まったのが一八七一年であり、その数は年間で七十万頭におよんだ。
ところが、山口仙之助と牧野富三郎がオマハで伊藤博文の一行と別れた一八七二年三月、アビリーンの運命を変える決定が下される。
牛のロングドライブに関与しない周辺住民が、テキサス熱への恐れやカウボーイたちの乱暴な振る舞いに業を煮やし、テキサスの牧場主に牛の立ち入り禁止を正式に伝えたのである。こうしてアビリーンが牛の売買を独占していた時代は終わりを告げる。一八七一年は繁栄の最後の年となった。
だが、牛のロングドライブがなくなった訳ではなかった。「牛の町」の主役がとってかわっただけのことだった。牛売買の拠点に名乗りをあげる町は後を絶たなかった。
