

- 2019年04月02日更新
- 画 しゅんしゅん
一の十
見合い相手の裕子は、同じ自動車部の四学年後輩だった。
祐司が卒業した年の新入生になる。現役時代、主務という、主将に次ぐ役職を勤めていた祐司は、卒業後も頻繁に部室に出入りしていた。だから、浮き世離れしたお嬢さんの新入生がいて、「ごきげんよう」とあだ名されていたことは知っていた。
いつだったか、差し入れの鯛焼きを持って部室を訪ねたところ、裕子が一人でそこにいて、本当に「ごきげんよう」と声をかけられて仰天したことをよく覚えている。ああ、あれが富士屋ホテルの一人娘だったのかと、その時、祐司は合点したのだった。
裕子は、不思議な女性だった。
品のいい目鼻立ちではあったけれど、顔の造作は地味で、決して人目を引くような美人ではない。それなのに、態度や立ち居振る舞いは、まるで絶世の美女か、さもなくば女王のようなのだった。周囲の人たちは、自分を支えるために存在すると、自分が世界の中心であると、微塵の疑いもなく信じている。傲慢というのでもない、底なしの無邪気とでも言うべきか。
少し困ったような上目遣いの瞳で見つめられると、金縛りにでもあったように、裕子の要望を聞き入れてしまう、そんな得体の知れないパワーを持っていた。
そして、無防備なほど、感情を表に出す女性でもあった。
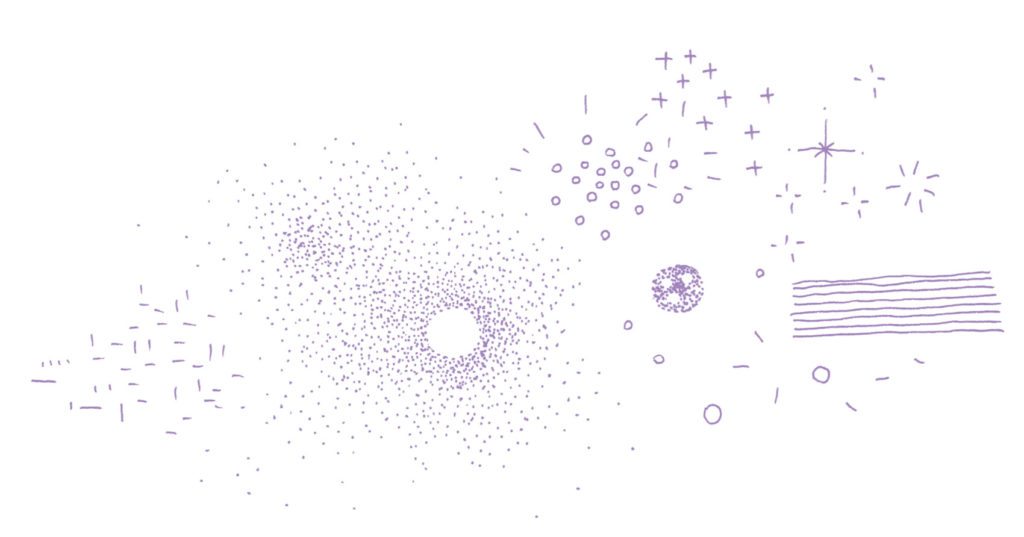
初めて会った時、祐司は、すぐに裕子が自分に異性としての好意を抱いていることを悟った。後になって、見合い話が持ち上がる以前から、時々部室を訪れる祐司に恋心を抱いていたことを打ち明けられた。
祐司には、親しい幼なじみの女性がいて、異性としての好意も抱いていた。相手もそうであると意識もしていた。だが、はっきり意思表示をする機会が無いまま、時が過ぎていた。
もし、この見合い話が持ち上がらなかったら、しかるべき時期に想いを伝え、平凡な結婚をしたことだろう。しかし、運命は、そうならなかった。
裕子との結婚を決意したのは、彼女の瞳が放つ得体の知れないパワーにからめとられた部分もあったけれど、最大の理由は、祐司の野心であった。富士屋ホテルのオーナー社長から娘婿にと請われたのである。当時、勤めていた商事会社にいるより、人生に大きな可能性が開けるような気がした。しかも、堅吉は、結婚の条件として、アメリカ留学の資金援助を申し出てきた。
そして、富士屋ホテルに運命を殉ずる決意をした。
裕子との結婚は、すなわちホテルとの結婚でもあった。
赤い欄干の不思議な館は、そう決意した時から、ゲストとして想像を膨らませて見上げる存在から、自らが守り継承すべきものになった。そして、情景は日常となり、感傷的な想像が入り込む余地はなくなった。
だが、虎造の訪問と、彼がカミングアウトした神風楼という遊郭との関係は、祐司に忘れていた好奇心を膨らませ、初めてこの場所を訪れた時の印象を蘇らせたのだった。
「ネクタリン・ナンバーナイン……」
祐司は、忘れようにも忘れられなくなったその名前を、もう一度、静かにつぶやいて、フェニックスハウスの階段を一歩ずつ踏みしめながら上がっていった。
