

- 2019年09月01日更新
- 画 しゅんしゅん
二の八
秋の気配が立ち始める頃、祐司は、山口虎造をあらためて富士屋ホテルに招待した。
突然の訪問とはいえ、オーキッドラウンジでコーヒー一杯しか出さなかったことに罪悪感のようなものを感じていたからだ。外国人墓地にジョン・エドワード・コリアーの墓を訪ねてから、その思いは、より顕著になった。富士屋ホテルとの縁を取り戻すため、箱根に来てくれた思いに答えるには、ドラゴンホールに招待しなければ完結しない、と思ったのである。
招待は休日のランチで、私も同席した。
待ち合わせのロビーにあらわれた虎造は、予想していた革ジャンとサングラスではなく、グレーのスーツを着ていた。彫りの深い顔立ちは、確かに西洋人の血を感じさせ、赤い幾何学模様のネクタイが個性的ではあったが、写真で見たのとは別人に思えた。
「はじめまして」
「祐司さんのお嬢さんですな。これは、これは。お目にかかれて光栄です。山口虎造と申します」
「よろしくお願い致します」
予想していた風貌と違うのを怪訝に思う気持ちが表情に出たのだろうか、虎造は聞きもしないのに答えた。
「富士屋ホテルの西洋料理におよばれするなら、ワインの一杯も頂きたいですし、今日は電車に乗って参りました」
「父が撮ったバイクの写真を拝見していたものですから、印象が違って驚きました」
「ははは、今日は、精一杯めかし込んできましたよ」
「そんなことを申し上げては失礼だろう。恐縮です」
祐司はそう言いながら、虎造をドラゴンホールに誘った。案内したのは、堅吉の家族がいつも座っていたテーブルだった。
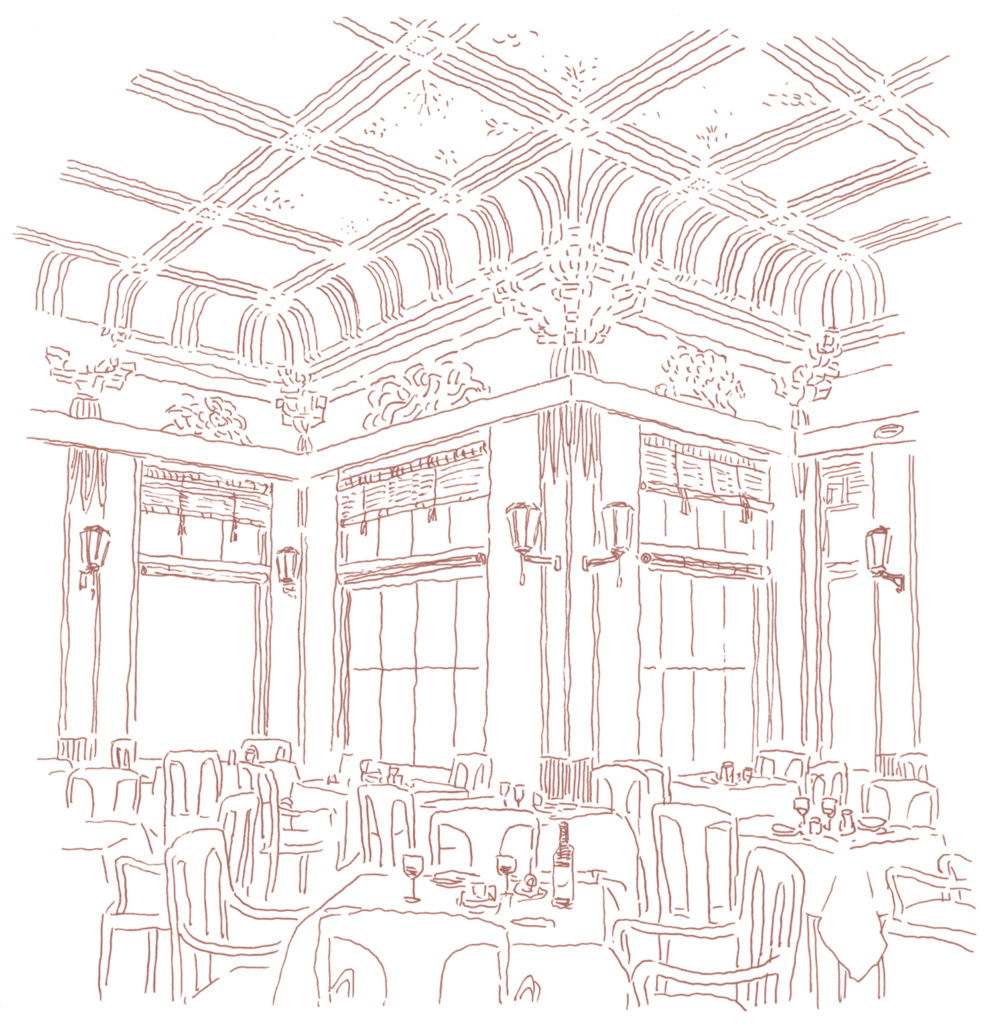
ドラゴンホールは、創業者仙之助の長女の婿、正造の時代に竣工した建物である。もともと正造が座っていたテーブルだと、祐司は堅吉に聞かされた。ヨーロッパでは、家族経営のいいホテルでは、オーナーファミリーがダイニングルームで食事をする習慣がある、わが家もそれに習ったと、私も母裕子から聞いた記憶がある。
山口家のテーブルは、入り口から向かって右手の角にあった。
窓からの眺めはあまりよくないが、ダイニングルーム全体を見渡すのに好都合の席だった。上席というのなら、このテーブルではない。同じ窓際でも、もっと眺めのいい席がある。
虎造をここに案内したのは、山口家の親戚として、彼を迎え入れたい気持ちがあったからだった。
